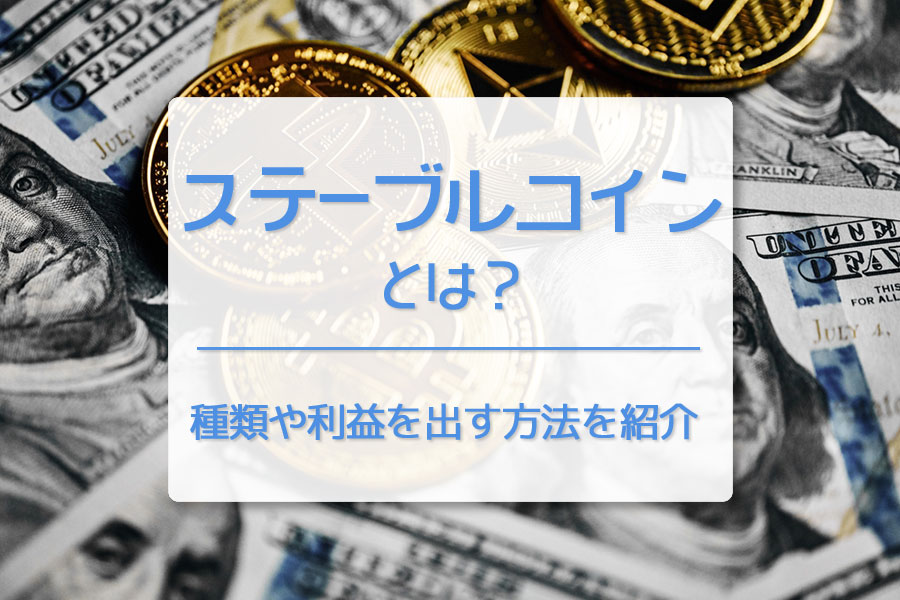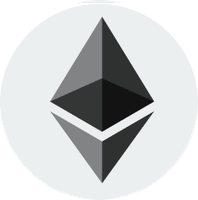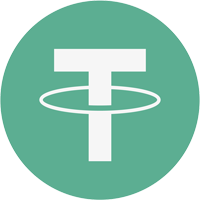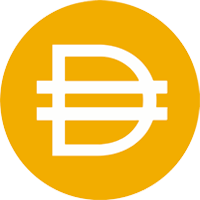ステーブルコインとは? 種類や利益を出す方法を紹介
2024.11.01
ステーブルコインとは、法定通貨や仮想通貨(暗号資産)、コモディティと連動することにより、価格が安定して推移する仮想通貨(暗号資産)です。数ある仮想通貨(暗号資産)の中でもトップ10に入るステーブルコインもあり、運用初心者にもおすすめできるので関心を持っている方もいるでしょう。
しかし一口にステーブルコインと言ってもその種類はさまざまであり、メリットだけでなくデメリットも存在します。ステーブルコインを効果的に運用するなら各種類の特徴を押さえた上で、利益を出す方法などを把握しておかなければなりません。

そこで本記事では、ステーブルコインの概要や種類、利益を出す方法などを解説します。記事後半ではステーブルコインの将来性やメリット・デメリット、おすすめの銘柄もご紹介するのでぜひ参考にしてください。
ステーブルコインとは
ステーブルコインとは、米ドルや日本円などの法定通貨や貴金属・自然エネルギーなどのコモディティと連動するよう設計された仮想通貨(暗号資産)です。
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの銘柄は時価総額こそ高く注目されているものの、価格は不安定です。決済手段としてより広く普及するには、実用性の面で欠点があるでしょう。
その状況下で誕生したのが、価格が安定して推移するステーブルコインです。市場規模は拡大しつつあり、資産の避難先としての活用や法整備により、今後もさらに需要が増すと期待されています。
ビットコイン(BTC)との違い
ステーブルコインとビットコイン(BTC)の違いは、ボラティリティの大きさです。
ステーブルコインであるUSテザー(USDT)の2018年10月から2024年4月の5年半の間の価格は、対ドルで見ると2%以内で推移しています。
一方で、同時期のビットコイン(BTC)の最低価格は約3,000ドル、最高価格は7万ドル以上です。
ステーブルコインは資産を安全に運用する目的で、ビットコイン(BTC)は価格変動で大きな利益を出す目的(投機目的)で利用されます。
※価格は2024年6月時点の情報です。

ステーブルコインの種類
一口にステーブルコインと言っても、担保方法によって以下の4つに分類できます。
- 法定通貨担保型
- 仮想通貨担保型
- アルゴリズム型
- コモディティ型
仮想通貨(暗号資産)運用、とりわけステーブルコインを運用するならそれぞれの違いを押さえておくことが欠かせません。各担保方法の仕組みや具体例を詳しくみていきましょう。
法定通貨担保型
法定通貨担保型のステーブルコインは、米ドルやユーロ、日本円などの法定通貨によって価値が裏付けられています。米ドルに紐付けられているステーブルコインには、以下の銘柄が挙げられます。
- USテザー(USDT)
- USDコイン(USDC)
いずれも2024年6月時点で、時価総額ランキングトップ10に入っている銘柄です。
Binance USD (BUSD)はどうなった?
Binance USD (BUSD)は、米ドルにペッグしたステーブルコインの一つで、2022年11月には時価総額が233億ドルを超えるなど、人気のステーブルコインでしたが、現在の時価総額は約7000万ドル(2024.6月)であり、99.7%以上減少しています。
BUSDが現在、ほとんど流通していない理由は、米国の証券取引委員会(SEC)による規制強化と訴訟です。2023年6月、SECはBinanceとその創設者Changpeng Zhaoに対して、無登録の証券取引所を運営していたとして訴訟を起こしました
この訴訟を受けて、Binance.USは米ドルの入金と出金を停止する決定を下しました。BinanceのBUSDが規制上の問題を引き起こし、さらに米国証券取引委員会(SEC)による訴訟の対象となったことがBUSDの流通停止の一因となっています。これらの要因により、BUSDの流通が大幅に制限され、現在の市場での取引量が減少しています
法定通貨担保型のステーブルコインは、発行元が償還に十分対応できるほどの裏付け資産を持っていることが前提です。この前提があるおかげで、価格の安定性が保たれます。
信頼がないとユーザーに利用してもらえず普及しない可能性があるため、ステーブルコインの発行元は裏付け資産に関するレポートや報告書を公開しているところもあります。法定通貨担保型のステーブルコインを運用するなら、過去の価格推移や将来性の予測に加えて、裏付け資産が十分にあるかもあわせて確認しましょう。


USDコイン(USDC)とは?
特徴や価格動向、将来性について解説
仮想通貨担保型
仮想通貨(暗号資産)担保型のステーブルコインは、ステーブルコイン以外の仮想通貨(暗号資産)により価値が裏付けられています。代表的な仮想通貨(暗号資産)担保型のステーブルコインは、ダイ(DAI)やsUSD(SUSD)などです。
ダイ(DAI)を例にして、どのように価格を安定化させているのか見ていきましょう。
一般に法定通貨と比較して、仮想通貨(暗号資産)は価格変動の度合い(ボラティリティ)が大きいため、裏付け資産とするには不安が残ります。そのためダイ(DAI)では、過剰担保制度が取られています。
過剰担保とは、発行するダイ(DAI)より多額の仮想通貨(暗号資産)を担保に入れる方法です。2024年6月現在、ダイ(DAI)の担保率は150%以上です。これにより、担保とする仮想通貨(暗号資産)の価格が下がっても安定した価格推移を取れます。
また、万が一担保としている仮想通貨(暗号資産)が過剰担保を上回る勢いで暴落するケースにも対応できるようなシステムも導入されています。裏付け資産が最低担保率を下回った場合、追加で担保を投入するか、もしくは強制決済で資産を差し押さえられるかを選択しなければなりません。
上記のような仕組みをとることで、ボラティリティの大きい仮想通貨(暗号資産)を裏付け資産としたステーブルコインの発行が可能です。
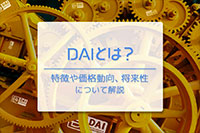
仮想通貨(暗号資産)DAIとは?
特徴や将来性を徹底解説
アルゴリズム型
アルゴリズム型のステーブルコインは無担保型とも呼ばれ、特定の裏付け資産ではなく、あらかじめ定められたアルゴリズムによって価格を安定させる仕組みです。アルゴリズム型のステーブルコインには、以下の銘柄が挙げられます。
- マジック・インターネット・マネー(MIM)
- フラックス(FRAX)
- TerraUSD(UST)
- ニュートリノUSD(USDN)
各ステーブルコインでアルゴリズムには違いが見られますが、いずれも市場の需給を元に銘柄の供給量を調整する点では共通しています。
例として、米ドルと1対1で推移するステーブルコインの場合を考えてみましょう。仮想通貨(暗号資産)1枚あたりの価格が1ドルを上回る場合は供給量を増やし、価格を下げます。反対に1ドルを下回る場合は供給量を減らし、希少価値を高め価格を上昇させます。
ただし、アルゴリズム型のステーブルコインは裏付け資産がないので、暴落するリスクを抱えている点が問題です。TerraUSD(UST)」は2022年5月に米ドルとディペッグ(ペッグが外れること)を起こし、約1ヶ月で価格が100分の1になる大暴落を起こしました。TerraUSD(UST)と米ドルと連動させる役割を担っていたルナ(LUNA)も大暴落を起こし再起不能に至っています。
アルゴリズム型のステーブルコインを運用する際は、どのようなアルゴリズムで価格を維持しているのか、それには暴落リスクはないのか、運営元は信頼できる団体なのかなどを十分確認してください。
コモディティ型
コモディティ型のステーブルコインは、貴金属や自然エネルギー、農作物などのコモディティ(現物資産)を担保に発行されています。経済の影響を受けにくいとされるコモディティを活用し、価格の安定化を図っている点が特徴です。
コモディティ型のステーブルコインには、三井物産デジタルコモデティーズが発行する金(ゴールド)の価格に連動して推移するジパングコイン(ZPG)が挙げられます。親会社の三井物産がロンドン市場で購入した金現物をステーブルコインの裏付け資産とし、金(ゴールド)1グラムとジパングコイン(ZPG)1枚あたりの価格が同じになるよう発行されます。ステーブルコインの価格維持の原理原則は、法定通貨担保型と同じです。
コモディティ型のステーブルコインは、運搬や分割が困難なコモディティの取引を簡単にすることが期待されています。2024年6月時点でジパングコイン(ZPG)は実際の金(ゴールド)との交換はできませんが、将来的には交換可能になると公式が発表しています。

ステーブルコインの今後や将来性
ステーブルコインの今後の将来性は、以下のように予想されています。
- 法整備が整い安心して利用できるようになる
- 市場規模が拡大する
- マルチチェーンに対応する
価格が安定して推移するとされていたステーブルコインですが、TerraUSD(UST)の崩壊をきっかけに安全性が疑問視されました。日本でも法整備が進められ、2023年6月に新たに施行された改正資金決済法では、ステーブルコインを取り扱う業者の規制が明記されています。
法整備が整った結果、ユーザーは安心してステーブルコインを利用できるようになるでしょう。企業にとってもメリットのある法改正で、企業間送金や決済にステーブルコインが利用されると予想されています。
また、ステーブルコインの市場規模はより拡大する見込みがあります。ステーブルコイン部門の時価総額ランキング上位4銘柄の2020年の時価総額は0.6兆円でしたが、2021年8月末には12兆円を突破しました。現在ではテザーUSD・USDコイン(USDC)・DAIの3銘柄で24兆円を超えており、米ドルと連動するステーブルコインの需要は拡大を続けています。
法整備が整ったこともあり、今後ステーブルコインの利用や活用が増えれば、市場規模がますます拡大するでしょう。そうなるとステーブルコインへの需要は増し、価格の安定性がより強固なものになると考えられます。
さらに、ステーブルコインがマルチチェーンに対応する動きが加速するとも予想されています。仮想通貨(暗号資産)には独立したブロックチェーン上に存在し、互換性がないものもありますが、相互互換性のあるプロジェクトが誕生しているのが近年のトレンドです。
ステーブルコインも例外ではなく、USDコイン(USDC)はイーサリアムブロックチェーンに加えて、ソラナやステラ、トロンなどのブロックチェーン上でも発行されます。
マルチチェーンに対応し利便性が増せば、今以上にさまざまなプロジェクトで活用されるでしょう。

ステーブルコインで利益を出す方法
ステーブルコインで利益を出すには、以下に示す方法が挙げられます。
- イールドファーミング・ステーキング
- アービトラージ
- レンディング
イールドファーミング・ステーキング
イールドファーミングは、DeFi取引所に仮想通貨(暗号資産)を預け入れ、流動性を提供する見返りに利息を得られます。
一方のステーキングは、対象の仮想通貨(暗号資産)を保有してブロックチェーンのネットワークに参加することで、インカムゲインが得られる仕組みです。
アービトラージ
アービトラージ取引との関係性
アービトラージ取引は、ステーブルコインの価格連動を保つために重要な役割を果たします。ステーブルコインが法定通貨の価格から乖離した場合、アービトラージ取引がその差を埋める動きを引き起こします。
価格が下落した場合:例えば、ステーブルコインの価格が1ドルより低く取引されている場合、トレーダーはそのコインを安く買い、それを1ドルで発行者に償還します。この過程で、トレーダーは差額分の利益を得ることができ、同時に市場からステーブルコインが減少するため、価格が上昇します。
価格が上昇した場合:逆に、ステーブルコインが1ドルより高く取引されている場合、トレーダーは発行者から1ドルで新しいコインを購入し、市場で高値で売却します。この過程で、トレーダーは利益を得ると同時に、市場に新たなステーブルコインが供給されるため、価格が下がります。
アービトラージ取引の運用利益
アービトラージ取引は、価格の乖離を利用して利益を上げる戦略です。ステーブルコインの場合、以下のような方法で運用利益が得られます。
乖離の瞬間を捉える:価格が目標値から外れた瞬間を見計らって取引を行うことで、確実に利益を上げることができます。このためには、高速かつ効率的な取引システムが必要です。
取引手数料を考慮:利益を最大化するためには、取引手数料を最小限に抑える必要があります。多くのアービトラージトレーダーは、取引所間の手数料を比較し、最も有利な取引所を選択します。
リスク管理:アービトラージ取引は比較的低リスクですが、全くリスクがないわけではありません。例えば、取引所の信用リスクや取引の遅延などが考えられます。これらのリスクを管理するために、トレーダーは分散投資やリスクヘッジ戦略を用います。
アービトラージ取引によって、ステーブルコインの価格は常に目標値に近づくように自動的に調整されます。このメカニズムが、ステーブルコインの価格安定性を保つ重要な要素となっています。
レンディング
レンディングは保有する仮想通貨(暗号資産)を第三者に貸し出し、利息を得る運用手法です。難しい知識や自分で運用する手間は不要でありながら、年利数%台と高い利率で運用できます。
レンディングはボラティリティの小ささをカバーできるため、ステーブルコインを効果的に運用したい方におすすめです。レンディングによる運用を考えている方は、BitLendingのご利用をご検討ください。


仮想通貨(暗号資産)レンディングとは?
メリット・デメリットを解説

ステーブルコインのメリット
ステーブルコインのメリットには、以下の3つが挙げられます。
- ボラティリティが小さい
- 高利率で運用できる
- 法定通貨の代替となり得る
- 資産の避難先となる
各メリットを見ていきましょう。
1つ目のメリットは、ボラティリティが小さい点です。一般的に仮想通貨(暗号資産)はボラティリティが大きく、短期間で価格が高騰・暴落するのは珍しくありません。適切なタイミングで参入すれば利益を狙える一方、タイミングが悪ければ大きな損失を出す可能性があります。しかし、価格を正確に予測するのは運用上級者でも容易ではありません。
その点ステーブルコインなら価格が安定して推移するので、大きな損失を出すリスクを抑えられます。リスクを最低限にして運用したい方には、最適な選択肢でしょう。
2つ目のメリットは、高利率で運用できる点です。アービトラージ取引による利益は、市場の価格乖離を利用するため、高利率での運用が可能です。価格の乖離が発生するたびに取引を行うことで、短期間での利益を積み重ねることができます。これにより、ステーブルコインは投資家にとって魅力的な運用手段となり、特に低リスクで高利率の運用を求める投資家に適しています。また、ステーブルコインの安定性は、他の暗号資産と比較してもリスクが低いため、アービトラージ取引を通じた運用が非常に効果的です。
3つ目のメリットは、法定通貨の代替となり得る点です。米ドルにペッグするステーブルコインを保有すれば、事実上米ドルを保有していることになります。米ドルが法定通貨として採用されている国・地域であっても、ステーブルコインが利用できるなら日本円を米ドルに両替する手間が省けます。
4つ目のメリットは、資産の避難先となる点です。効率的に資産運用をするなら、暴落リスクに備えるために、保有する資産はなるべく分散させるのが良いとされています。
日本円・米ドル・ユーロなどの法定通貨や株式・債券に加えてステーブルコインを保有しておけば、リスクを分散できます。
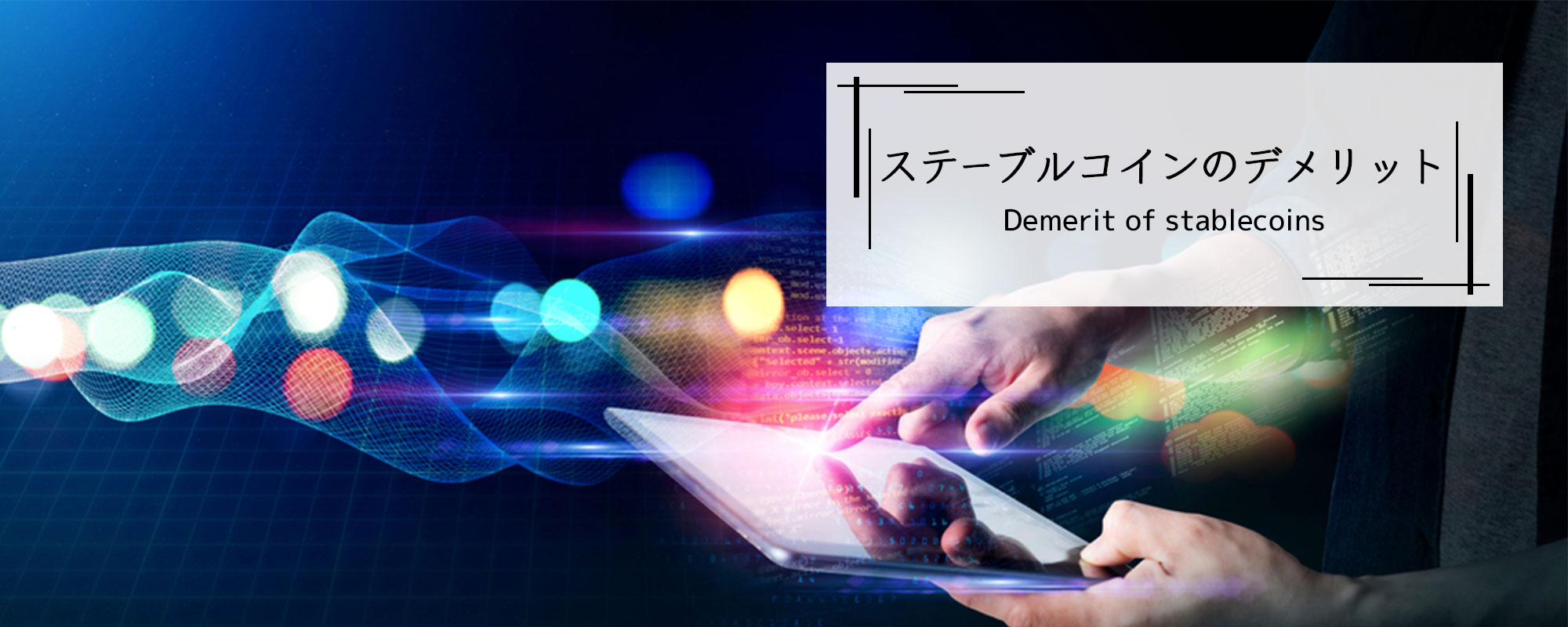
ステーブルコインのデメリット
ステーブルコインを運用するなら、メリットに加えてデメリットも押さえておくべきです。ステーブルコインのデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 価格崩壊のリスクがある
- 現物取引では大きな利益を狙えない
それぞれのデメリットを見ていきましょう。
ステーブルコインは価格が安定して推移する点がメリットですが、必ずしも価格が崩壊しないわけではありません。過去にはアルゴリズム型のステーブルコイン「TerraUSD(UST)」が価格崩壊に至った事例があります。価格崩壊するリスクも頭に入れた上で、運営元の信頼度や担保の仕組みを考慮して運用するよう心がけてください。
また大きな利益を出すのには向いていない点も、ステーブルコインのデメリットです。仮想通貨(暗号資産)は短期間で高騰するケースもしばしばあり、購入タイミングによっては数倍〜数十倍以上の値上がりに期待できます。
しかしステーブルコインの場合は、ボラティリティが小さいため、購入金額と売却金額の差で利益を出す現物取引では大きな利益は狙えません。この手の取引で利益を出すなら、それ相応の元本が必要です。
現物取引で大きな利益を得るのが難しいステーブルコインですが、高い利率で運用できるレンディングならボラティリティの小ささをカバーできるでしょう。
ステーブルコインの中でもおすすめの銘柄
ステーブルコインには数多くの銘柄があります。仮想通貨(暗号資産)運用初心者の方にとって、どの銘柄を運用すべきか判断するのは容易ではないでしょう。
ステーブルコインの運用を考えている方に幅広くおすすめできるのが、以下の3つの銘柄です。
- USテザー(USDT)
- USコイン(USDC)
- ダイ(DAI)
上記の銘柄は2023年10月時点で、ステーブルコイン部門の時価総額ランキングにおいてトップ3に入っています。各銘柄の特徴や時価総額、過去の価格推移、将来性などを見ていきましょう。
USテザー(USDT)
USテザー(USDT)は、Tether Limited社の発行する、イーサリアムベースのステーブルコインです。仮想通貨(暗号資産)時価総額ランキングでビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)に次ぐ第3位と注目度の高さがうかがえます。
米ドルと連動し、安定して価格推移するUSテザー(USDT)を基軸通貨として取り扱っている企業はいくつかあります。2023年10月時点でUSテザー(USDT)を購入できる国内仮想通貨(暗号資産)取引所はありませんが、法整備が整いつつあるため、上場する可能性は十分考えられるでしょう。
また、利便性の高さからスイスのルガーノ市ではビットコイン(BTC)とスイスフランに連動するステーブルコインのLVGAとともに法定通貨に採用されています。同市では、公共サービスや税金の支払いなどにUSテザー(USDT)を利用できます。

仮想通貨(暗号資産)テザー(USDT)とは?
メリット・デメリットや今後の動向を解説
USコイン(USDC)
USDコイン(USDC)は、サークル社とCoinbaseが共同で発行するステーブルコインです。時価総額ランキングではソラナについでトップ6にランクインしています。
USDコイン(USDC)の特徴は、信頼性が高い点です。価格が米ドルに連動している点や、大手金融機関のゴールドマン・サックスからのバックアップを受けている点は、取引する際の安心材料になるでしょう。
また、ニューヨーク州から仮想通貨(暗号資産)関連事業の許可書を得ている他、大手会計事務所から監査を受け、資産保有証明書を公開しています。公的機関に認められているうえ、透明性の高い取引がなされている点もUSDコイン(USDC)が信頼性の高い仮想通貨(暗号資産)だと言われる所以です。

USDコイン(USDC)とは?
特徴や価格動向、将来性について解説
ダイ(DAI)
ダイ(DAI)は、自立分散型組織のMaker DAOが発行する仮想通貨(暗号資産)担保型のステーブルコインです。時価総額ランキングではトップ20以内に位置しています。
多くのDApps(分散型アプリケーション)の開発に活用されている点が、DAIの特徴です。NFTマーケットプレイスや仮想通貨(暗号資産)ウォレットなどで採用されており、すでに400以上のサービス・プロダクトで利用されています。トークン規格はイーサリアムブロックチェーンのERC-20が用いられているので、互換性の高さも持ち合わせています。
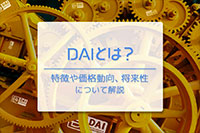
仮想通貨(暗号資産)DAIとは?
特徴や将来性を徹底解説

ステーブルコインを堅実に運用したいならプロに任せよう
本記事では、ステーブルコインの分類や将来性、メリット・デメリットなどを解説しました。ステーブルコインには幅広い活用法があるため、今後ますます市場規模は拡大するでしょう。
価格が安定して推移する点が魅力ですが、価格が暴落するリスクもあるので、どのような担保形式なのか、運営元は信頼できるのかを確認してください。
ステーブルコインの運用方法にはいくつかありますが、レンディングならボラティリティの小ささをカバーしつつ、利益を狙える点が特徴です
レンディングサービスを提供するBtiLendingでは、以下の銘柄を表示の利率で運用できます。