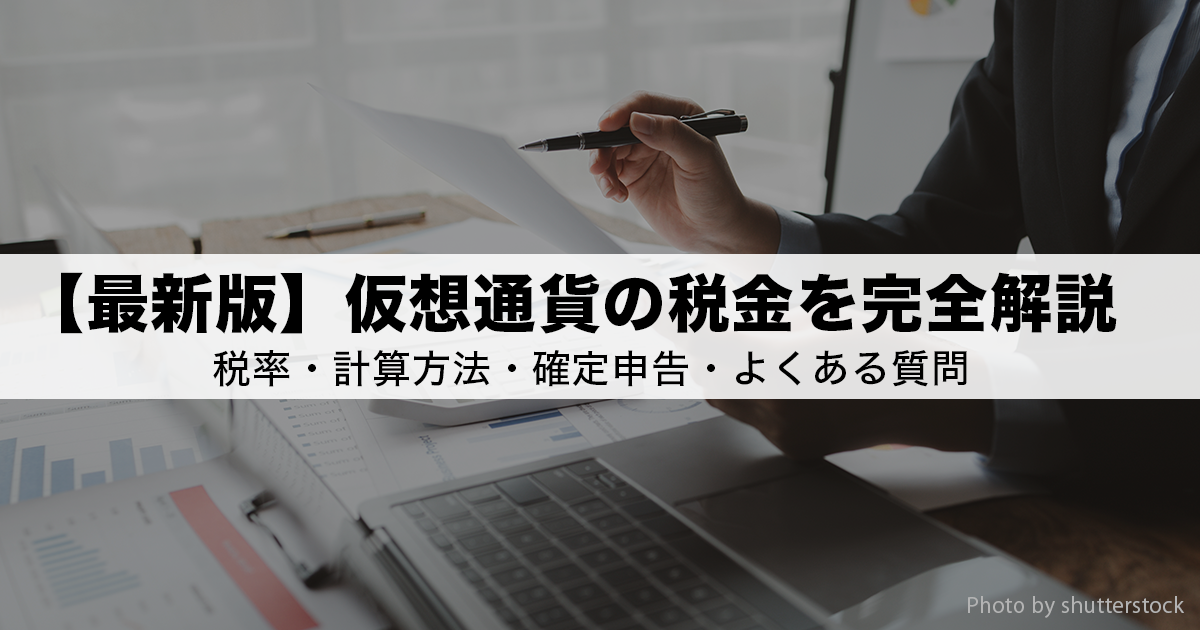【最新版】仮想通貨の税金を完全解説|税率・計算方法・確定申告・よくある質問
2025.12.09
本記事は、カオーリア会計事務所 (代表・税理士 藤本剛平)の監修のもと、最新の法改正・通達を踏まえて、仮想通貨(暗号資産)の税金について解説しています。
仮想通貨(暗号資産)を取り巻く税制度は、依然として発展途上にあり、毎年のように法改正や運用ルールの変更が行われています。2025年も例外ではなく、取引を行う個人投資家にとって見逃せない動きが多数あります。
中でも、2026年からの導入が検討されている「申告分離課税」や「損益通算の解禁」は、税制の根本を揺るがす大型改正案として注目されています。今後の投資戦略や納税方針に大きく関わる可能性があるため、動向を早めに把握しておくことが重要です。
本記事では、2025年末時点で明らかになっている税制改正のポイントや、影響を受けやすい取引パターンを整理しながら、確定申告や納税準備にどう活かせるかを、税理士監修のもとでわかりやすく解説してまいります。
※ 2025年11月27日時点の情報です。制度改正により内容が変わる可能性があります。
この記事でわかること
2026年に向けた転換点:申告分離課税導入の可能性と注目ポイント
現在、雑所得として課税され、最大55%の税率が適用されている仮想通貨(暗号資産)取引ですが、2026年以降をめどに株式・FXと同様の「申告分離課税」への移行が本格的に検討されています。
導入の期待度はどれくらい?
業界団体・金融庁・与党は「暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品として位置づけ、投資しやすい環境を整備する」という方向性で合意に近づいており、改正の実現可能性は年々高まっています。たとえば、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)や金融庁も2026年度税制改正要望として「暗号資産課税見直し(分離課税含む)」を正式に提出しています。しかし、法改正・制度設計・報告義務整備など複数のハードルが残っており、「2026年1月から確実」と断言できる段階ではありません。
出典:
「web3 提言 2025」自由民主党の Web3 ワーキンググループ
注目すべきポイント
- 税率の大幅な見直し:現在は所得に応じて5〜45%+住民税10%(最大約55%)ですが、分離課税になると一律約20.315%が想定されています。
- 損益通算・繰越控除の解禁:現行制度では他の所得との損益通算や翌年以降への損失繰越が認められていませんが、分離課税導入時にはこれらが併設される可能性が指摘されています。
- 対象範囲と適用条件の明確化:国内取引所の上場銘柄・特定口座対応・取引所間送金・DeFi・海外取引所など、どこで行われた取引が「分離課税対象」になるのかは今後の議論ポイントです。
- 申告・報告手続きの簡易化:制度導入と同時に「年間損益報告書」や「特定口座制度」の仮想通貨(暗号資産)版整備も検討されており、確定申告の負担軽減が期待されます。
投資家が今から準備すべきこと
分離課税の実現に備え、以下の3つのアクションを推奨します。
- 現在の損益を明確に把握する → 分離課税適用後は損益計算のルールも変わるため、税率のシュミレーションも兼ねて、取得原価・損益額は事前に適切に把握しておきましょう。
- 取引履歴や取得原価・円換算レート等の証憑を整理し保存する → 制度移行時に遡って申告資料の提出が求められる可能性があります。
- 対象取引所・銘柄・取引形態(国内/海外/DeFi)の動向を注視する → 適用範囲が限定的な場合、その範囲に合わせた投資戦略の検討が必要です。
本セクションはあくまで「検討中」の制度改正を前提としていますが、仮に2026年以降に実現すれば仮想通貨(暗号資産)投資の税制環境にとって最大級の転換点となる可能性があります。今から準備しておく価値は十分にあります。

仮想通貨(暗号資産)の課税区分と税率の基本
仮想通貨(暗号資産)によって得た利益は、原則として「雑所得」として総合課税されるのが現在の日本の制度です。ここでは、仮想通貨(暗号資産)における課税の考え方と、適用される税率、損益通算や繰越控除の可否について整理します。
総合課税・雑所得の考え方
仮想通貨(暗号資産)の売却や他の仮想通貨(暗号資産)との交換などで得た利益は、個人においては「雑所得」に分類され、他の給与所得や事業所得などと合算して総合課税の対象となります。
- 所得金額に応じて5%~45%の所得税率が適用され、さらに住民税(10%)が上乗せされます。
- 申告分離課税(株式やFXのような一律20.315%)は、現時点では適用されません。
- 法人の場合は法人税の対象となり、個人とは異なる扱いになります。
なお、仮想通貨(暗号資産)による報酬(例:ステーキング・マイニング・エアドロップ等)も原則として雑所得扱いとなります。
《出典》
暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)〔FAQ・令和6年12月最終改訂PDF〕|国税庁
税率の早見表(所得帯別/住民税含む)
| 課税所得額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 | 合計税率(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 | 10% | 約15% |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 | 10% | 約20% |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 | 10% | 約30% |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 | 10% | 約33% |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 | 10% | 約43% |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 | 10% | 約50% |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 | 10% | 約55% |
※課税所得=総所得-各種控除(基礎控除、社会保険料控除、扶養控除など)
※住民税は一律10%ですが、自治体により微差あり
《出典》
損益通算・繰越の可否
現在の制度では、仮想通貨(暗号資産)の雑所得に関しては以下の制限があります。
- 損益通算は不可:他の所得(給与・不動産・事業所得など)との損益通算はできません。
※雑所得同士であれば損益通算することができます。 - 繰越控除も不可:前年の損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
- ただし、同じ年内の仮想通貨(暗号資産)間の損益は合算可能(例:BTCで50万円の利益、ETHで30万円の損失 → 差引20万円の雑所得として計上可)。
将来的には、「申告分離課税」への移行とともに損益通算や繰越が認められる制度改正も検討されていますが、現行制度では厳格に制限されていますので注意が必要です。
《出典》

損益計算の基本とよくある落とし穴
仮想通貨(暗号資産)の税金において、もっとも重要かつミスが起きやすいのが収支の計算方法です。売買損益の計算は単純なようでいて、取得原価の算定方法や、トークンの入送金のタイミング・手数料・取引時のレートなどを適切に反映する必要があります。
ここでは、損益計算の基本ルールと、間違いやすいポイントを詳しく解説いたします。
取得原価(移動平均/総平均)の選択と一貫性
仮想通貨(暗号資産)の取得原価(=その通貨を得たときの日本円での価格)は、「移動平均法」または「総平均法」のいずれかを選んで計算します。
- 移動平均法:法人の原則的な計算方法。その都度、取得のたびに平均原価を更新する方法。取引履歴が多い場合は計算負担が増えます。
- 総平均法:個人の原則的な計算方法。その年のすべての取得を合計し、平均単価を出す方法。年末にまとめて計算するスタイルに向いています。
いずれを選んでも構いませんが、一度選んだ方法はその年内で一貫して使う必要があります。計算方法を途中で変更したい場合は、税務署に届け出を提出する必要があります。
取引所間送金・手数料・スプレッドの扱い
複数の取引所を利用している場合、通貨の移動(送金)によって税務処理が発生する可能性があります。
- 送金そのものに課税は原則なしですが、手数料が発生する場合、購入時は取得原価に含め、それ以外のときは別途費用処理します。
- 手数料が仮想通貨(暗号資産)建ての場合(例:BTCで送金し、0.0005 BTCが手数料)、その時点の円換算額で評価し、費用として記録が必要です。また、手数料支払い時の時価と取得原価の差額も損益額に計上します。
- スプレッド(買値と売値の差)、売買時の日時、取引数量、取引資産の内容を明確に記録していないと、実際の損益がずれて計算されてしまうため、取引明細の保存が重要です。
円建て換算レートの決め方と記録
仮想通貨(暗号資産)の売買や取得時には、必ず日本円での評価額を算定しなければなりません。
- 為替レートの基準は「取得・譲渡時点の実勢レート(取引所の価格)」を使用します。
- 国税庁では特定のレート指定はしておらず、「継続して合理的な方法」であれば認められるとしています(例:coingekkoなどの暗号資産価額掲載サイトの情報、損益計算ソフト側で提供する価額データなど)。
- 同じ方法を一貫して用いることが前提条件です。都度、異なる基準で評価すると不正確と判断される恐れがあります。
また、記録には取引所の画面スクリーンショットやCSV明細などの証憑(取引や業務の事実を証明する書類)が有効です。
《出典》
具体例:ビットコインの税金を計算する方法
購入と売却をそれぞれ1回ずつ行うケースと、売却するまでに複数回購入するケースに分けて見ていきましょう。
まずは、購入と売却をそれぞれ1回ずつ行うケースの具体例を紹介します。
- 3000万円で3BTC購入
- 1BTC=1500万円になったタイミングで1BTCを売却
1BTCを購入するのにかかった費用は3000万円÷3=1000万円です。所得金額は1500万円-1000万円=500万円となります。購入と売却がともに1回のケースでは、総平均法と移動平均法で所得金額は変わりません。
続いて、売却するまでに複数回購入するケース(売買はすべて同一年度)を見ていきましょう。
- 1000万円で1BTC購入
- 1200万円で1BTC購入
- 1500万円で1BTC売却
- 1400万円で1BTC購入
総平均法では、合計金額の3600万円を購入枚数の3枚で割った、1200万円を1枚あたりの単価とみなします。したがって所得金額は、1500万円 – 1200万円 = 300万円です。
移動平均法では、2.の取引が終わった時点で一度平均を計算します。単価は2200万円 ÷ 2 =1100万円です。その後売却しているので、所得金額は1500万円 – 1100万円 = 400万円となります。
上記のケースでは、総平均法のほうが所得金額が少なく計算されますが、保有数量がゼロになるまで全て売却し終わった最終的な総所得額は同じになります。

確定申告の流れと必要書類
仮想通貨(暗号資産)で利益が出た場合、原則として確定申告が必要です。特に会社員であっても、年間20万円以上の雑所得がある場合は申告義務が発生します。(住民税は20万円未満でも申告義務アリ)。
このセクションでは、確定申告の準備から提出までの流れと、必要な書類・よくあるミスについて解説いたします。
事前準備チェックリスト(ダウンロードすべき明細等)
確定申告に向けて、以下の資料を事前に整理・保存しておくことで、スムーズかつ正確な申告が可能になります。
- 各取引所の年間取引履歴(CSV形式が望ましい)
- メタマスクなどのウォレットアドレス
- 取引所やウォレットごとの期末時点での仮想通貨(暗号資産)の保有数量を表示した画面のスクリーンショット
- その他、上記年間取引履歴などからは取得できない取引の明細(日時・数量・仮想通貨(暗号資産)の種類の記載必須)
これらは最低でも7年間保存が必要とされるため、デジタルで(必要に応じて紙で)確実な保管体制を整えましょう。
確定申告のステップとやり方
仮想通貨(暗号資産)で利益が出た場合、確定申告の流れは以下の手順に沿って進めるのが基本です。e-Taxを使うことで自宅から申告可能なため、早めの準備が推奨されます。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告の具体的な流れ
Step1 取引所から取引履歴を取得する
まず取引所から取引履歴をダウンロードしましょう。主に以下の情報が記載されています。
- 取引日時
- 取引内容
- 購入・売却数量と金額
- 手数料
この取引履歴は、確定申告時に収支を記載するための根拠資料として非常に重要です。失くさないよう保存しておきましょう。また、取引所によっては過去の履歴を出してくれないところもあるので毎年必ずダウンロードしておきましょう。
Step2 計算書をダウンロード・作成する
国税庁のサイトから、仮想通貨(暗号資産)専用の計算書(エクセル形式)をダウンロードします。
取引数量が多い場合は、クリプタクトなどの損益計算ソフトの利用を検討してください。また、計算結果については必ず保管してください。
- 移動平均法用/総平均法用の2種類あり、計算方法に応じて選択
- 年間取引報告書を使う場合は、総平均法用を推奨とされています
計算書には以下の情報を入力します。
- 仮想通貨(暗号資産)名
- 年始残高・年中の購入/売却数量・金額
- 支払手数料
- 円換算時のレートとその基準(取得時点価格など)
Step3 確定申告書類に記入する
作成した損益計算書をもとに、確定申告書を作成します。
- 仮想通貨(暗号資産)の利益は「雑所得」欄に記入
- 所得が20万円を超えると会社員でも申告義務が発生
Step4 確定申告書を提出する(e-Taxまたは郵送)
作成した書類を所轄の税務署へ提出します。
- 提出期間は毎年2月16日〜3月15日(平年)
- e-Taxを使う場合は、マイナンバーカード+ICカードリーダー、またはスマホによるマイナ認証が必要
- 郵送・持参でも提出可能ですが、e-Taxのほうがスムーズです
※仮想通貨(暗号資産)に関する取引明細の添付義務はありませんが、税務署から照会があった場合に対応できるよう、書類やスクリーンショットは保存しておきましょう。
Step5 納税する
確定申告後、算出された税額を納付します。納税方法は以下から選べます。
- 振替納税(口座振替)
- e-Tax経由でのオンライン納付
- クレジットカード払い
- コンビニ納付(QRコード対応)
- 金融機関や税務署での現金納付
納税期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、期限内の納付を忘れずに行いましょう。
よくあるミス(証憑不足/計上漏れ)
以下のようなミスが多発しています。ご注意ください。
- 取引履歴の計上漏れ
- 円換算レートの不統一(日によって基準を変えてしまう)
- 計算した仮想通貨(暗号資産)の期末保有数量が実際のものと異なる
- NFT売買やDeFi取引の課税を見落とす
こうしたミスは、後から税務署に指摘された場合、延滞税や加算税の対象となるため、早めかつ正確な記帳と申告が重要です。
《出典》

行為別の課税ポイント
仮想通貨(暗号資産)による所得は、その行為(使い方)によって課税の扱いが変わる点が非常に重要です。たとえば、単なる売買と、ステーキングによる利回りでは、課税の時期や所得区分が異なる場合があります。
ここでは、主要な行為別に税務上のポイントを簡潔に整理し、詳細を知りたい方向けには特化記事へのリンクも設けております。
売買・交換・スワップ
- 仮想通貨(暗号資産)を日本円に換金した場合、または他の仮想通貨(暗号資産)に交換した場合、それだけではなく、他のサービス・モノと交換した場合、差益は雑所得として課税対象です。
- スワップ(例:BTC→ETH)は、いったんBTCを売却したと見なされます。
- 原則として都度課税(取得時との差額を計算)となり、個人の場合、含み益の段階では非課税です。です。
ステーキング・マイニング・エアドロップ
- これらは「取得時に価値が発生する」と見なされるため、付与時点での時価によって雑所得として課税されます。
- 付与時点の時価記録と、その後の売却・譲渡との損益記録を分けておくことが重要です。
レンディング
- 仮想通貨(暗号資産)を第三者や取引所へ貸し出して利回りを得た場合も、受取時の時価で雑所得として課税されます。
- 受領通貨が異なる場合は、その通貨の取得価額としても管理が必要です。
- 詳細は、以下の特化記事で詳しく解説しています。
→ レンディング 税金の詳細はこちら
ビットコイン固有論点
- ハードフォーク(分岐)で新たな通貨が付与された場合、その通貨の取得時点の時価が課税対象となります。ただし、ハードフォークによる新通貨付与の場合、時価がないことが多いため、その場合は時価は0円として処理します。
- BTCを分割(例:Sats単位)して送金する際も、取得原価の按分計算(取得価額を比例配分して計算)が必要です。
- 詳細は、以下の特化記事をご覧ください。
→ ビットコイン 税金の詳細はこちら
《出典》
記帳・保存・監査対応
仮想通貨(暗号資産)の確定申告においては、帳簿の作成と証憑の保存が極めて重要です。税務署からの問い合わせや将来の監査に耐えるためには、正確かつ継続的な記録体制が求められます。
《出典》

よくある質問(総合)
仮想通貨(暗号資産)に関する税務は複雑で、多くの方が共通して疑問に感じる点があります。初心者から経験者までがよく抱く疑問をQ&A形式でまとめました。
確定申告をしなかったらどうなる?
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が発生します。
無申告加算税は自主的な期限後申告をしたか、税務調査の通知を受けたかなどによって加算割合が5-30%と変動します。場合によっては重加算税(40%)が課されるリスクもあります。
延滞税は「納付すべき税額× 延滞税の割合 × 経過日数÷365日」で計算されます。税務署は銀行や取引所の取引データや場合によってはブロックチェーン上の入送金履歴も把握しているため、申告しないリスクは非常に高いです。
確定申告はいつまでにすれば良い?
毎年2月16日〜3月15日が提出期限です。間に合わなかった場合でも、速やかに期限後申告を行いましょう。
経費は何が計上可能?
仮想通貨(暗号資産)に関連する出費のうち、必要経費として計上できるものを活用しましょう。
| 区分 | 経費例 |
|---|---|
| 全額認められる | 取得費、手数料、セミナー代、税理士費用、10万円以下の専用PC・スマホ等 |
| 部分的に認められる | 通信費、兼用デバイス ※家事按分が必要 |
| 認められない | 投資仲間との会食、10万円超デバイスの一括経費化など |
取引所をまたいだ損益計算は?
はい、全取引所を合算して年間の損益を計算する必要があります。国内外の取引所を併用している場合も、それぞれの取引履歴を統合して申告しましょう。
円転していない含み益は課税?
いいえ、保有中の価格変動による含み益は課税対象ではありません(法人は課税対象)。ただし、他通貨への交換や商品購入などで実現した場合は課税対象です。
仮想通貨(暗号資産)デビットカードもサービスによってはそのサービスに預け入れた時点で課税対象となることがあるので、利用前に規約をよく読みましょう。
《出典》
仮想通貨(暗号資産)の税金と確定申告方法|freee 会計知識ベース
※ 本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断は税理士等の専門家へご相談ください。
監修者プロフィール

税理士・カオーリア会計事務所代表
藤本剛平
暗号資産・NFT専門税理士として個人から大企業まで様々な税務・損益計算の対応実績を有する。(公財)大阪産業局主催Web3特化型アクセラレーション「SUITCH」の特別メンター。税理士向け専門誌「税務弘報」にて特別対談記事、税務記事を多数掲載。「Accord Tax Review」にて税法論文を執筆。近畿税理士会主催税理士向けセミナー、Bitbank、Zaif主催の税金セミナーの講師としても活躍中。暗号資産・NFT損益計算サービス「Cryptorch」開発協力。
著書(共著)「事例でわかる!NFT・暗号資産の税務」(中央経済社)