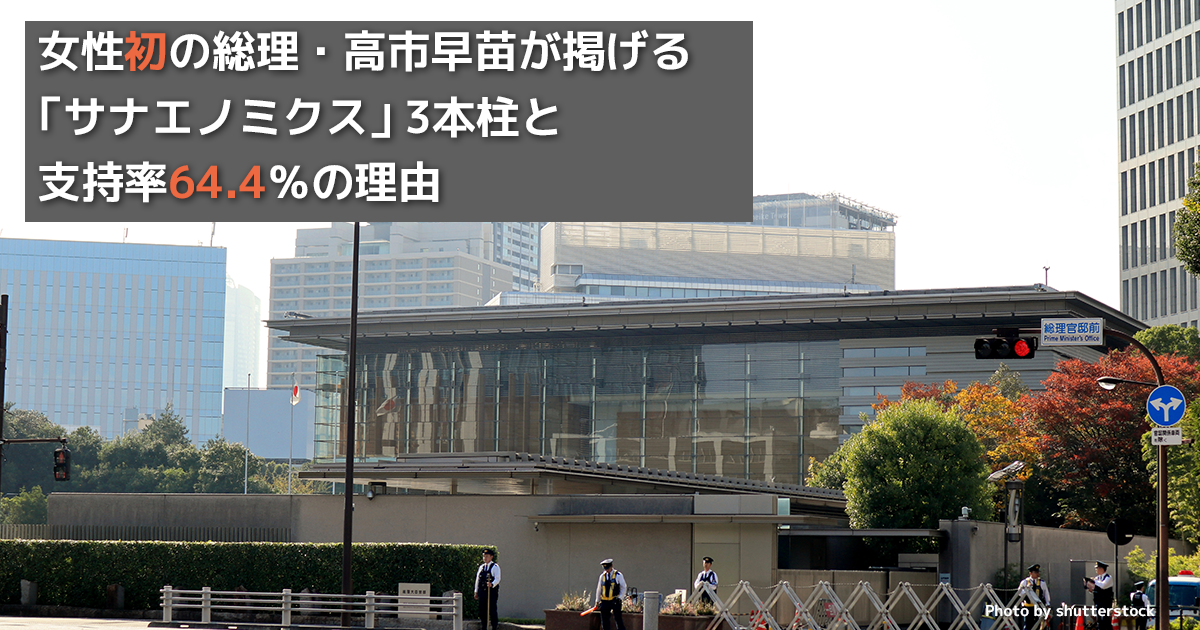女性初の総理・高市早苗が掲げる「サナエノミクス」3本柱と支持率64.4%の理由
2025.10.23
女性初の総裁選勝利と首相指名、そして高市内閣の発足
10月4日に自由民主党の総裁選が実施され、高市早苗氏が女性として初の総裁に就任しました。さらに10月21日の首相指名において衆参両院で指名され、女性として初の内閣総理大臣が誕生しました。即日組閣が行われ、高市内閣がスタートしています。
自民党は10月4日に総裁選の開票を実施し、10月21日に国会の首相指名を経て組閣手続きを完了し発足しました。
世論の初期反応:支持率と不支持率の水準
共同通信社が行った緊急電話世論調査(10月21〜22日実施)によると、新内閣の支持率は64.4%でした。これは内閣がスタートした時の石破内閣の50.7%、岸田内閣の55.7%を上回る水準です。直近9月の石破内閣支持率は34.5%で、不支持率は51.4%でした。今回の高市内閣では不支持率が23.2%と大きく低下しており、自民党にとって挽回の好機となったようです。
発足時の支持率比較
| 内閣 | 調査タイミング | 支持率 | 不支持率 |
|---|---|---|---|
| 高市内閣 | 発足直後(10月21〜22日) | 64.4% | 23.2% |
| 石破内閣 | 発足時 | 50.7% | — |
| 岸田内閣 | 発足時 | 55.7% | — |
直近(発足前月)の石破内閣
| 時点 | 支持率 | 不支持率 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 34.5% | 51.4% |
国民が期待する政策領域
高市内閣に期待する政策としては、物価高対策が38.9%と最も多く、次いで年金などの社会保障が11.7%、政治とカネ問題が8.1%、議員定数削減が3.6%、副首都構想が0.7%となりました。国民の物価に対する不満の高まりがうかがえる結果です。
| 政策項目 | 割合 |
|---|---|
| 物価高対策 | 38.9% |
| 年金などの社会保障 | 11.7% |
| 政治とカネ問題 | 8.1% |
| 議員定数削減 | 3.6% |
| 副首都構想 | 0.7% |
首相が掲げる主要政策と初動の焦点
高市首相は記者会見で、最初に「物価高対策」を掲げ、具体的には「ガソリン暫定税率の廃止」と「103万円の壁の引き上げ」をあげました。さらに、従来から掲げている「危機管理投資」「経済安全保障」「食料安全保障」「エネルギー安全保障」などを重要政策としています。また国民の手取り収入にかかわるものとして「高校の無償化」「給食の無償化」を掲げ、石破政権で支持を得られなかった給付金政策に関しては「給付付税額控除」の導入を検討しています。
「サナエノミクス」3本柱
- 金融緩和
- 財政出動
- 危機管理と成長投資
高市首相の政策は「アベノミクス」をもじった「サナエノミクス」と呼ばれ、「金融緩和」「財政出動」「危機管理と成長投資」の3本柱が注目されています。株式市場では、これらに関連する企業が「高市トレード」として買われていますが、高市内閣は日本維新の会の閣外協力を基盤とする少数与党のため、政策の実現にはほかの野党の協力も必要になる見通しです。
政権運営の展望と解散カード
高市首相は、内閣の支持率を見極めながら政権運営を円滑に進めるため、解散を視野に入れているとみられます。今後のスタートダッシュでどのような政策を展開するのか、注目が集まっています。
今後の高市首相及び新閣僚の動向を引き続き注視していきたいと思います。
初入閣や閣僚人事の注目点
経済安全保障や危機管理を担うポストの人選が焦点となっており、初入閣の顔ぶれや与野党協力の枠組みが政策実現のスピードを左右するとみられます。市場や有権者の関心は「物価・賃上げ・可処分所得」に集中しており、ガソリン税、年収の壁、給付付税額控除といった家計に直結する論点の進展が早期の評価を左右するでしょう。
暗号資産を巡る政策方針と今後の見通し
高市首相は経済安全保障や成長投資の一環として、暗号資産やブロックチェーン分野の政策整備にも前向きな姿勢を示しています。特に、スタートアップ企業の育成と資金調達の円滑化を目的とした税制改革については「現実的な環境整備を急ぐ」と述べています。
具体的には、法人が保有する暗号資産の含み益課税の見直しや、トークン発行を通じた資金調達(IEOやトークンエコノミー)の制度的安定化が期待されています。また、Web3.0やDeFi(分散型金融)関連のスタートアップ支援を推進し、税務上の取扱いや国際的な規制調和を図る方向性がみられます。
政策実現の鍵
実現のカギとなるのは、金融庁及び経済産業省との政策連携と、国会での超党派的な合意形成です。税制改正については年度末の与党税制改正大綱が焦点となりますが、高市内閣が「経済安全保障と成長投資」を両立する方針を掲げていることから、暗号資産を実体経済の一部として取り込む方向で議論が進む可能性が高いです。
技術発展を促す枠組みづくり
一方で、国際的なマネーロンダリング(AML)やテロ資金供与防止(CFT)に関する基準への適合も求められており、規制緩和と国際ルールの両立が大きな課題となります。高市首相が「革新と秩序の両立」を掲げる以上、暗号資産分野においても過度な規制強化ではなく、技術発展を促す枠組みづくりが重視されるでしょう。
今後の見通しとしては、2026年度までに税制面での一定の前進が見込まれ、ブロックチェーン関連事業に対する投資環境が改善する可能性があります。高市政権が掲げる「サナエノミクス」の3本柱のなかでも、デジタル資産政策は成長投資の中核として注目される分野となりそうです。