WebX2025完全レポート|政府が描いたWeb3・暗号資産の未来と税制改革の道筋
2025.09.03
WebX2025とは?──政府・業界・海外リーダーが集った日本最大のWeb3.0カンファレンス
2025年8月25日・26日。猛暑の東京・芝公園に、世界中からWeb3.0の未来を議論するためにキープレイヤーたちが集結した。開催されたのは「WebX2025」──日本発のグローバルWeb3.0カンファレンスである。14,000人を超える参加者は、単なるテック系イベントの枠を超え、国家戦略と民間イノベーションが交差する“場”を目撃することとなった。
このイベントの核心は、「日本がWeb3.0で世界をリードできるのか?」という問いである。技術立国としての再起、少子化による社会構造変化、そしてデジタル主権を巡る国際競争──あらゆるテーマが、WebX2025という舞台上で結びついた。
開催概要:会場・参加者の顔ぶれ
舞台は東京都港区・芝公園。増上寺と東京タワーに挟まれた日本有数の歴史と都市性を兼ね備えた「ザ・プリンスパークタワー東京」で、「リアル×デジタル」が交錯する象徴的な会場設計がなされた。巨大スクリーンのメインステージ、テーマ別ブース、スタートアップ展示、Web3.0プロジェクトピッチ、インフルエンサーエリアまで、多層的に構成されていた。
イベントには、国内の暗号資産業界のリーダーはもちろん、金融機関関係者、シンクタンク研究員、海外VC、NFTクリエイター、そしてエンタメ・アニメ産業の著名人まで、多岐にわたる有識者らが来場。その規模と多様性は、日本におけるWeb3.0産業の「厚みと広がり」を物語っていた。
政府首脳の登壇──Web3.0が“国家戦略”として語られた瞬間
最大のサプライズともいえたのが、石破茂内閣総理大臣の登壇だった。首相は壇上で「世界は今、100年に1度の産業転換点を迎えている」とし、Web3.0という新領域を「単なるトレンドやバズワードではなく、日本の主権と経済の将来に直結するテーマ」と位置づけた。
さらに石破首相は、少子化による経済縮小のなかで、分散型ネットワークを活用したあらたな資本主義モデルの必要性に触れ、「国家がイノベーションの障害ではなく、触媒でなければならない」と明言。これは、日本の政治トップがWeb3.0を国家レベルで支援することを明言した、歴史的な瞬間といえるだろう。
続く武藤経産相も、「世界のWeb3.0政策はすでに“加速フェーズ”に入っている」と述べ、米国やシンガポールなどの法整備の進展を背景に「世界の潮流に乗り遅れないようにしたい」と語った。その真摯な言葉には、過去の「慎重過ぎた日本行政」への自己批判もにじんでいた。

注目セッションまとめ:暗号資産・Web3.0の焦点
WebX2025の白眉は、政府首脳による開会挨拶にとどまらなかった。2日間にわたって開催されたセッションでは、技術、金融、規制、社会実装、エンターテインメントなど、Web3.0を構成するさまざまなテーマが交差し、まさに“多層的”な議論が展開された。
なかでもひときわ注目を集めたのが、暗号資産を巡る「税制と投資」のセッション群である。制度整備を進める政府、活用を模索する事業者、慎重な投資家──立場の異なる登壇者たちが1つの議題のもとに集結したことで、リアルな温度差と課題感が浮き彫りとなった。
円建てステーブルコインと金融制度の未来
加藤勝信財務相は、日本初の円建てステーブルコイン発行事例に触れ、「ステーブルコインは単なる決済手段にとどまらず、リテール決済、国際貿易決済など、幅広い分野で活用が見込まれる」と位置づけた。
同時に、DeFiやDAO(分散型自律組織)などWeb3.0特有のガバナンス構造にも言及し、「利用者保護とイノベーション促進のバランスを取った環境整備が必要」と語る姿勢は、金融当局としては異例の柔軟性を示したといえる。
税制改革の議論:暗号資産に20%の申告分離課税を導入へ
このテーマで中心的な役割をはたしたのは、bitFlyer創業者の加納裕三氏だ。加納氏は、現行制度(住民税とあわせて最大55%の課税)がいかに個人投資家の心理的・経済的障壁になっているかを詳細に説明。「このままでは、海外に流出したWeb3.0人材・資金は2度と戻ってこない」と危機感をあらわにした。
具体的には、暗号資産による所得を「株式等と同様に20%の申告分離課税とし、損失繰越制度を導入する」ことが提言されている。自民党・金融庁内でもこの方針が議論されており、2026年の税制改正大綱への盛り込みを目指す動きが加速している。
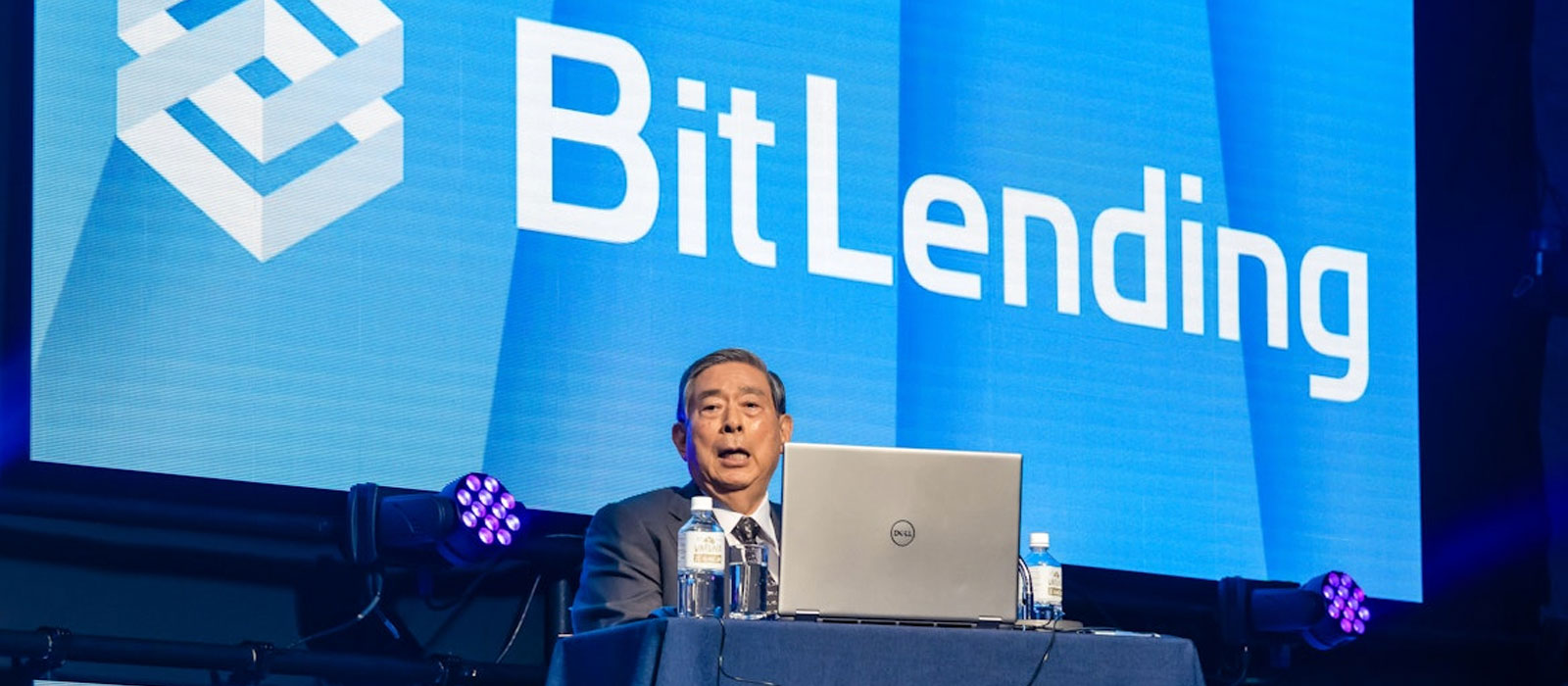
メディア×金融 革命前夜:情報とマネーはどこに向かうか(北尾吉孝氏×堀江貴文氏)
WebX2025のなかでも大きな注目を浴びたのが、SBIホールディングス代表取締役会長兼社長の北尾吉孝氏と、実業家・著述家の堀江貴文氏による対談セッションだ。テーマは「メディア×金融 革命前夜:情報とマネーはどこに向かうか」という刺激的な題材で、金融サービスと情報流通の融合に関する未来的な議論が展開された。
北尾氏は、SBIグループが持つ約4,200万を超える金融口座基盤を活用し、「法定通貨に裏付けられたステーブルコイン決済システム」の構築を進めていると明かした。これは、価格の安定性と瞬時・低コスト決済を実現し、EC・サブスクリプション・国際送金など幅広い領域での応用が期待されるインフラである。

また、堀江氏は日本の既存メディア産業の課題を鋭く指摘。広告依存型ビジネスモデルはコンテンツの魅力を損なうとした上で、「DAOのガバナンストークンを活用したあらたな収益構造」が、次のメディア革命のカギになるとの見解を示した。さらに、ステーブルコインを活用した取り組みについて「日本にとって最後のチャンス」と発言し、会場の注目を集めた。
この対談では、SBIによる「ステーブルコイン決済」という金融インフラ構築と、メディアと金融の融合による価値交換の仕組みの再創造という、両極的だが補完し合う構想が鮮明に描かれた。北尾氏による規制遵守を重視したモデル構築を進める姿勢は、国内におけるWeb3.0の実用化を加速させるための力強いメッセージとして映った。
投資家テスタ氏の視点:「暗号資産投資は慎重に」発言の背景
実力と人気を兼ね揃えた投資家として知られるテスタ氏が、暗号資産投資に関するセッションに登壇したことは大きいな注目を集めた。株式投資で100億円超の利益を積み重ね、個人投資家の間で絶大な影響力を持つテスタ氏は、これまで暗号資産について明確な発言を避けてきた。
セッション内では「わからないものには投資しない」という一貫したスタンスを披露し、リスク許容度と情報アクセスの非対称性に対する慎重な姿勢を崩さなかった。しかし、最後には「大暴落があれば買ってもいいかもしれない」と会場を沸かせ、興味自体は抱いていることを匂わせた。

暗号資産税制の現状と改革の動向
Web3.0産業の成長を支える根幹は、制度の整備である。なかでも、税制は最もダイレクトに投資行動に影響を与える分野であり、WebX2025でも多くのセッションで税制改正に関する要望が強調された。現在の日本の税制度では、暗号資産の取引等により生じた利益を「雑所得」として扱っており、その不合理性が兼ねてから指摘されてきた。
現行制度:最大55%の雑所得課税がもたらす弊害
2025年現在、暗号資産取引等で生じた利益は給与や事業所得と合算される「総合課税」の対象とされており、累進課税制度により最大55%の税率が適用される。この税制は、個人トレーダーが多い暗号資産市場にとって極めて高負担であり、加えて年間の損益通算・損失繰越ができないため、税制的には極めて不利な設計となっている。
この税制がもたらす結果として、海外への資産移転・法人登記・口座開設が増加し、日本市場の空洞化が進んでいる。言い換えれば、税制こそが日本のWeb3.0ビジネスにおける“参入障壁の本丸”なのだ。
改革案の方向性:申告分離課税と損失繰越の導入へ
bitFlyerを始めとした業界団体や、与党Web3.0政策推進派の議員らは、暗号資産の課税方式を「株式やETFと同等の20%の申告分離課税」に改めることを強く求めている。
この方針はすでに金融庁と財務省の有識者会議でも議論されており、「金融商品取引法への組み込み」とセットで制度化される可能性が高い。仮にこれが実現すれば、損失繰越控除や特定口座制度の導入も視野に入り、税務処理の簡素化と投資家の安心感向上が一気に進むだろう。
国際比較と制度整備の急務性
すでに米国ではビットコイン現物ETFなどが承認され、機関投資家の参入が活発化している。シンガポール、スイス、ドバイでは、税制面・法制度面でWeb3.0スタートアップの支援体制が整っており、国をあげてWeb3.0分野のエコシステム形成を進めている。
こうした国際的な潮流のなかで、日本が「税制後進国」のままであれば、優秀な起業家・開発者・投資家を自ら国外に追いやることになる。Web3.0が“国家間の経済戦争”と化す時代において、税制整備は単なる国内政策ではなく、外交的・戦略的課題でもある。

「AIの通貨はクリプトに」:Binance・CZ氏が描く未来の経済
WebX2025の注目セッションの1つとしては、Binance創業者・CZ氏を招いたFireside Chatがあげられる。モデレーターはCoinDesk編集者のBenjamin Schiller氏。CZ氏はグローバルな業界の潮流だけでなく、未来の通貨観を大胆に語った。
CZ氏はまず、トランプ政権による暗号資産政策の転換を振り返り、「2024年7月、トランプ氏が暗号資産支持を表明した時、私は“刑務所から出られた”ような気持ちだった」と語った。前政権の強硬姿勢に対する実感がにじみつつ、現在の政策スピードに期待を示した。
さらに未来予測として、「AIの通貨は暗号資産になる」と断言。AIエージェント同士の取引が増え、従来の法定通貨やクレジットカード決済を介した人間中心の構造から脱却することで、数百〜数千倍の経済活動がAIによる自律支払で完結すると指摘した。だからこそ、ブロックチェーンの“プログラム可能なAPI”としての優位性が活きるのだという構造論だ。
講演の後半では教育へのコミットも示され、CZ氏は「Giggle Academy」と名付けた教育プラットフォームを紹介。12億人以上が教育を受けられない現状を踏まえ、アプリを通じた学習によって「3億ドルで18年分の教育を提供できる」と語った。すでに50,000人以上のユーザーを持ち、大学をも超える規模に成長している点を強調した。
また、約12カ国の政府や国家元首への助言活動を行っていることも明かし、ステーブルコイン・CBDC・取引所といった規制と市場形成に関わる戦略的な立場での貢献を語った。
セッションの締めくくりとして若い起業家に向けたメッセージも印象的だった。「正しいこと=倫理的で価値あるプロダクトを作ること」に注力し、短期的な利益ではなく“情熱と価値の交差点”にこそ成功があると力強く語った。

テスタ氏と他投資家の対話から見える温度差
ここからは、先述したテスタ氏のセッションについて、より具体的に掘り下げていきたい。このセッションでは、個人投資家としての代表的な存在・テスタ氏と、暗号資産を中心に資産形成を行うJoe Takayama氏、そしてbitFlyerの加納氏が初めて顔をあわせた。
この特別対談は単なる意見交換にとどまらず、伝統的な投資観とWeb3.0的な価値観の“衝突”と“融合”を象徴する、印象的なセッションとなった。
テスタ氏の慎重なスタンス:「わからないものには投資しない」
テスタ氏はこれまで一貫して株式市場を中心に資産を築いてきた。テスタ氏の投資哲学は「理解できる企業にしか投資しない」というものであり、そのスタイルは暗号資産のようにボラティリティが高く、技術的に複雑な資産クラスとは本質的に相性が良くない。
実際、セッション中も「ブロックチェーンやトークン経済について、十分な理解が追いついていない」とし、暗号資産についての積極的な投資は避ける姿勢を貫いた。これは、初心者層にとって非常に誠実な発言でもあり、“わかるものに投資する”という原則が市場でいかに重要かを再認識させられる瞬間だった。
対するJoe Takayama氏の暗号資産への確信とETF期待
一方、Joe Takayama氏は、自らの資産のほとんどをビットコインとイーサリアムに振り分けている“暗号資産フルベット型”の投資家である。彼は「ブロックチェーン技術がもたらすインフラ革命は、インターネット黎明期と同じ構造を持っている」と語り、暗号資産が社会の基盤技術として定着していく未来に確信を持っていた。
特に注目されたのは、ビットコイン現物ETFの今後の動向と税制改革への期待についての発言だ。「制度さえ整えば、あらゆる資産運用の基盤に暗号資産が組み込まれる時代が来る。その最初の波に乗るか、見送るかで、リターンは劇的に変わる」と語る言葉には、自らの信念と実績に裏打ちされた説得力があった。
この温度差が日本の投資文化に与える示唆
このセッションで浮き彫りとなったのは、投資家における「情報リテラシーと制度理解のギャップ」だった。テスタ氏のような伝統的な金融商品を取引する投資家にとって、暗号資産は“未知の世界”であり、法的整備や情報の透明性が確保されない限り、参入は極めて慎重になる。
一方で、Joe氏のような先進的な投資家は、制度の不完全さをも“チャンス”として捉えており、むしろ混沌のなかに高いリターンを見出している。これは、今後の日本においてWeb3.0投資を普及させるためには、「教育」と「制度の簡素化」の両輪が不可欠であることを強く示している。

総括:WebX2025が示した「日本Web3.0・暗号資産の現在地」
政策・制度・市場環境の“三角同盟”がカギを握る
WebX2025は、単なる技術カンファレンスにとどまらず、「政策×制度×市場」が本格的に連携を始めた象徴的な場となった。政府の高官たちが明確に“国家戦略”としてWeb3.0を語り、民間のイノベーターたちがリアルな課題をぶつけ、個人投資家がその未来を占う──この構図は、まさに“産官民の臨界点”である。
2024年までの「ウォッチ・アンド・ウェイト」な姿勢から一転し、2025年は「行動と実装」のフェーズに突入したといえる。これは、Web3.0に関心のあるすべての人にとって、大きな転換点となるだろう。
直面する課題:スピード、制度設計、教育インフラの不整備
もちろん、課題は山積している。税制改革1つ取っても、法改正→政省令→施行と複数段階を要し、最短でも2027年に法律が施行される可能性があるとみられている。また、金融庁・財務省・経産省など関係省庁の連携や、地方自治体との規制サンドボックス実装も今後の焦点だ。
さらに一般層にとっては、暗号資産の基本的な知識、投資判断力、詐欺・ハッキングへのリテラシーなど、教育的アプローチがまだまだ足りていない。制度だけでなく、“人材と教育”の土台づくりが急務である。
WebXは終わらない──次なるフェーズへ
WebX2025は1つの「通過点」に過ぎない。むしろ、ここからが日本のWeb3.0の本番だ。Web3.0を国策として掲げた今、日本は“覚悟を試されるフェーズ”に入ったといえる。法整備、税制改革、教育、ユースケース創出……すべてが同時並行的に求められている。
AIが台頭するなか、Web3.0という分散型の思想が再評価される動きも強まっている。中央集権からの脱却、透明性、自由な価値移転──これらを日本がどう受け止め、社会実装していくのか。
WebXが照らした光を絶やさず、日本が再び「テクノロジー立国」として世界の舞台に立つことを、ここに強く期待したい。
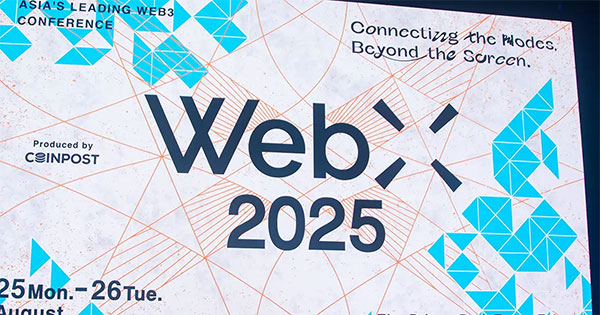
[Iolite記事]
日本からWeb3.0の現在地を発信 豪華な顔ぶれが揃った「WebX2025」をIoliteが徹底レポート!
