BTC・ETH・XRPはどう動く?FOMC後の金融・暗号資産市場総括|週間ビットコイン予想 2025.9/22-28
2025.09.22
先週のマーケットの振り返り
先週の金融市場と暗号資産市場は、16日-17日に開催されるFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果を待つ様子見ムードから始まりましたが、前週から続く9月の利下げ期待ムードが根強く、前半は底堅い展開となりました。
FOMCで利下げが決定した後、米国株式市場は利下げを好感して3指数とも史上最高値を更新して週を終えています。
一方、暗号資産市場は底堅い動きをみせていましたが、銘柄ごとにまちまちな動きとなり、週を通じては各銘柄とも幅のあるもみ合いの印象でした。
FOMCの決定が「政策転換の速度」ではなく「リスク管理」に重点を置いたものとして解釈された点が、株式には追い風、暗号資産には材料出尽くし感につながった可能性があります。
PMI(購買担当者景気指数)やPCE(個人消費支出)などの景気・物価系指標が次の方向性を左右しやすい地合いです。
9月15日(月)
15日の米国株式市場は前週の地合を引き継ぎ底堅く始まりました。個別企業の話題としてイーロン・マスク氏がテスラ株を10億ドル購入したことや、アルファベットの時価総額が3兆ドルを超えたこと、そして中国がエヌビディアを独占禁止法違反と判断したことなどがありました。全体としてはFOMCを控えた小じっかりもみ合いの日となりました。
BTCは115,000ドル約(1,700万円)台から始まり、116,700ドル(約1,720万円)台まで上昇しましたが、伸びきれず115,300ドル(約1,700万円)台半ばまで戻されました。
ETHも4,660ドル(約69万円)近辺まで買われましたが、4,460ドル(約66万円)台まで戻されています。
9月16日(火)
米国小売売上高が+0.6%と市場予想の+0.2%を上回り、3ヵ月連続で増加しました。物価の上昇が売上高を押し上げる一因になっていますが、引き続き消費が堅調である事を示しました。
ただ、FOMCの開催中ということもあり株式市場等の反応はほとんどありませんでした。また、株価は完全に様子見で小安い一日となりました。
BTCは地味ながら堅調で117,000ドル(約1,710万円)近くまで上昇し、116,800ドル(約1,710万円)近辺で終わりました。
ETHは4,530ドル(約67万円)への乗せもありましたが、上値は重く4,460ドルを割れて終わりました。
9月17日(水)
FOMCで0.25%の利下げが決定し、また年内の利下げについて2回と予想された事を好感してNYダウ平均は一時500ドル高まで上昇しました。
しかし、その後「噂で買って、事実で売る」動きがみられて下落し、260ドル高で終わりました。S&P500とNASDAQはやはり上値が重く、小安く終わりました。
暗号資産市場も似たような動きとなり、BTCは117,200ドル(約1,720万円)程度まで上昇しましたが、結局116,400ドル(約1,710万円)で終えました。
ETH、XRPは若干しっかりで、それぞれ4,500ドル台半ば、3.05ドル(約450円)台でした。
9月18日(木)
エヌビディアがインテルへ50億ドル出資することなどからIT・ハイテク株が上昇しました。
こうした動きを受けて暗号資産も上昇し、BTCは117,000ドル台、ETHは4,500ドル台半ば、XRPは3.10ドル(約455円)近辺へ上昇し終えています。
9月19日(金)
米国議会下院でつなぎ予算が可決された事を好感し株式市場は上昇しました。
またこの日は株式先物・株価指数オプション・個別株オプション取引の取引最終日でトリプル・ウォッチングの影響もあって3指数とも史上最高値を更新しました。
しかし、暗号資産は伸び悩みとなり、BTCが115,600ドル台(1,710万円台)、ETHが66万円台前半、XRPが440円台前半で週を終えています。
今週の経済イベントカレンダー
Calendar of Economic Events This Week
| 月 | 日 | 曜日 | 日本時間 | 国 | 経済イベント | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 23 | 火 | 21:30 | 米国 | 2025年第2四半期経常収支 | ★★★★☆ |
| 09 | 23 | 火 | 22:45 | 米国 | 製造業・サービス業PMI(購買担当者景気指数)9月 | ★★★★★ |
| 09 | 23 | 火 | 23:00 | 米国 | リッチモンド連銀製造業景気指数9月 | ★★★☆☆ |
| 09 | 24 | 水 | 23:00 | 米国 | 新築住宅販売件数8月 | ★★★★☆ |
| 09 | 25 | 木 | 21:30 | 米国 | 2025年第2四半期実質GDP | ★★★★☆ |
| 09 | 25 | 木 | 21:30 | 米国 | 耐久財受注8月 | ★★★★☆ |
| 09 | 25 | 木 | 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数9/14-9/20 | ★★★☆☆ |
| 09 | 25 | 木 | 23:00 | 米国 | 中古住宅販売件数8月 | ★★★★☆ |
| 09 | 26 | 金 | 21:30 | 米国 | PCE(個人消費支出)価格指数8月 | ★★★★☆ |
| 09 | 26 | 金 | 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数9月 | ★★★☆☆ |
[補足]
PMI(購買担当者景気指数)は、製造業・サービス業における購買担当者へのアンケートをもとに算出される代表的な先行指標です。 一般的に「50」を境に、景気拡大(50超)・縮小(50未満)を判断する目安となります。
ただし、注目すべきは単なる数値の上下ではありません。製造業PMIの「新規受注」や「輸出受注」は世界貿易の強弱を反映しやすく、サービス業PMIの「雇用」「価格」は国内消費やインフレ圧力を測る上で重要です。
たとえば、製造業が弱含んでもサービス業が堅調であれば「内需主導型の回復」が示唆されますし、両方が同時に低下すれば「景気の広範な減速シグナル」となります。またPMI速報値は月中に発表されるため、GDPや雇用統計よりも早く景気の方向感をつかめる点で投資家に重宝されています。
PCE(個人消費支出)価格指数は、FRBが金融政策を判断する際に最も重視するインフレ指標のひとつです。CPI(消費者物価指数)と比べてカバー範囲が広く、医療サービスや耐久財なども含むため「家計の実態に即した物価動向」をより的確に反映するといわれます。
特にコアPCE(食品・エネルギー除く)は変動要因を取り除いた基調インフレを示すため、FRBの利上げ・利下げ方針に直結します。直近では賃金上昇や住宅サービス価格がコアPCEを押し上げるかどうかが焦点です。
投資家がみるべきポイントは以下の3つです
- ① 前月比の伸び(インフレ圧力が加速しているか減速しているか)
- ② 年率換算の水準(2%目標にどれほど近いか)
- ③ サービス価格や住宅関連など「粘着性の高い項目」の動き
たとえば、コアPCEが市場予想を下回れば「インフレ沈静化 → 利下げ期待 → 株高・ドル安」に傾きやすく、 上振れすれば「インフレ根強さ → 金融引き締め長期化 → 株安・ドル高」という反応が出やすいと考えられます。
これらの結果は金利パスの見通しに直結しやすく、株式・債券・為替・暗号資産のボラティリティを高める傾向があります。
金融政策の評価と市場の視点
先週のFOMC後の記者会見でパウエルFRB議長は「リスクを管理するための利下げ」と述べ、また経済見通しで今後の利下げ予想は年内2回となりました。
パウエル議長のコメントや見通しからは、インフレを警戒する慎重なスタンスとみることができます。
今後は今回の利下げの大きな要因となっている雇用情勢がポイントとなり、雇用関連の経済指標の結果により市場は動いていくことになりそうです。
しかしインフレを警戒している金融当局としては、今週末に発表されるPCE価格指数の内容が金融当局の当面のスタンスを決めると考えられ、注目を集めています。
[視点の整理]
- ①雇用市場の減速度合い(失業率・雇用者数・賃金)
- ②インフレの粘着性(コアPCE・住居費・サービス価格)
- ③成長の持続性(個人消費・住宅)
という3点をチェックポイントに置くのが実務的です。
暗号資産:ETHとXRPの温度感
当面の大きな材料であったFOMCが終了し、大きな材料となっていた利下げが実施され、目先的には材料が出尽くしとなった感があります。
関税問題の1番の相手国である中国との関係が落ち着きつつあり、半導体問題も落ち着いたことから、IT・ハイテク株が動きやすくなりそうです。
株式市場は高値圏で警戒感を持ちつつも上値へトライしていきそうです。
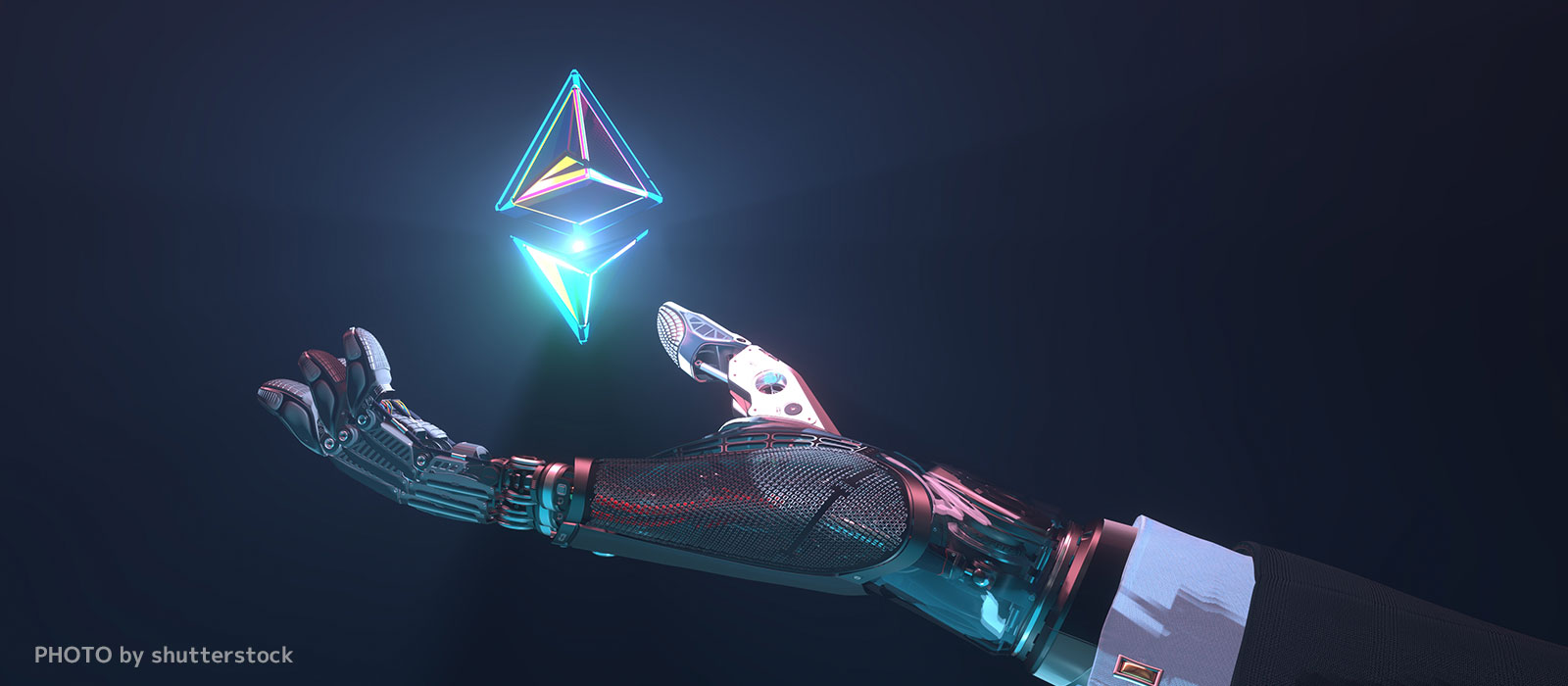
ヴィタリック・ブテリンが語るEthereumの今後10年
一方、暗号資産については、Ethereumが先週16日~19日にかけて大阪で「EDCON」というコミュニティカンファレンスを開催しました。このイベントは世界中の開発者・投資家・研究者が集うものであり、Ethereumコミュニティにとって技術・思想・資本の交流の場となりました。
特に注目されたのは、共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏による講演です。ブテリン氏はEthereumの短期・中期・長期にわたる開発計画を体系的に語りました。
具体的には、すでに進行している「The Merge(PoS移行)」の完成形を前提にした上で、次の段階である「The Surge(スケーラビリティ強化)」に焦点が当てられました。
これにより、レイヤー2(L2)ソリューションの普及や、データ処理効率を高めるDanksharding(データシャーディング)がカギになると強調しました。
さらに「The Verge」ではVerkle Trees導入によるノード運用の軽量化、「The Purge」では不要データの削減によるネットワーク効率改善、「The Splurge」ではその他の細かな最適化を予定しており、Ethereumが長期的に分散性・安全性・拡張性を兼ね備えたプラットフォームに成長する青写真を描きました。
この発表は単なる技術的な展望にとどまらず、グローバル金融インフラとしてのEthereumの立ち位置を示すものでもあります。会場では「ETHはインターネットの決済レイヤーとして成熟する可能性がある」という期待が高まり、NFTやDeFi、ステーブルコインといった既存ユースケースに加え、今後はDAT(Decentralized Autonomous Trusts)や公共セクターでの活用など、実経済への浸透が見込まれると議論されました。
こうしたロードマップは長期的視点での資産形成や投資判断に直結します。スケーラビリティとセキュリティの両立は暗号資産全体の課題ですが、Ethereumはこれを最も体系的に解決しようとしており、ビットコインに次ぐ基盤資産としての「信頼の積み上げ」が着実に進んでいます。
またスタンダード・チャータード銀行はETHがDAT企業からの恩恵を受けやすいとレポートしています。
さらに、米国SEC(証券取引委員会)はBTC・ETH・XRPなどの5銘柄へ集中的に投資するETFを承認しました。
XRPは法的リスクが後退
XRPは長らくSECとの法的係争が市場の重石となっていましたが、2023年以降の判決により「一部の取引においては証券ではない」と判断されたことで、法的リスクが一定程度後退しました。これにより米国内での取引所再上場や流動性回復が進み、投資家心理は改善傾向にあります。
技術的な側面では、XRPL(XRP Ledger)が高速かつ低コストの送金手段として評価されており、国際送金分野での活用が広がる可能性があります。特に、Ripple社が進めるODL(On-Demand Liquidity)はすでにアジア太平洋や中南米の銀行・決済事業者に導入されており、国際送金市場の効率化を後押ししています。
また、RippleはCBDC(中央銀行デジタル通貨)プラットフォームの開発支援にも取り組んでいます。これはXRPそのものの価格に直結するわけではありませんが、XRPL技術の信頼性が高まることでXRP需要を押し上げる可能性があります。
このようにアルトコインを巡る環境はフォローへと進んでおり、今後の展開が楽しみになってきています。
暗号資産は銘柄特有の材料に対する感応度が高く、ネットワークのアップグレード、流動性の供給源(ETF・取引所上場・ステーブルコイン需給)、規制ニュースのトーンによって温度差が生まれやすい点に留意が必要です。
このような周辺環境の変化を受けてBTCも徐々に下値を切り上げるのではないでしょうか。
年末に向けて前向きにみていきたいと考えています。
BTC積立企画
2023年6月から月毎に10万円分の暗号資産を実際に積み立てていき、そのポートフォリオを公開する企画です。ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、日本の取引所でも取り扱われており、米ドルとペッグ(連動)するステーブルコインであるダイ(DAI)を対象としています。
これまでの暗号資産積み立ての状況
Accumulation Status
[期間:2023.06.05 〜 2026.01.26]
ポートフォリオの現在の資産価値
円
含み益(現在の資産価値 - 合計積立金額)
円
利益率
%
積み立て回数
16 回
合計積立金額
1,600,000 円
ポートフォリオの構成
ポートフォリオ
| 銘柄 | シンボル | 対円レート | 保有数量 | 日本円換算 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン | BTC | [BTC/JPY]円 | 0.1523 BTC | 円 | % |
| イーサリアム | ETH | [ETH/JPY]円 | 1.8884 ETH | 円 | % |
| ダイ | DAI | [DAI/JPY]円 | 80 DAI | 円 | % |
