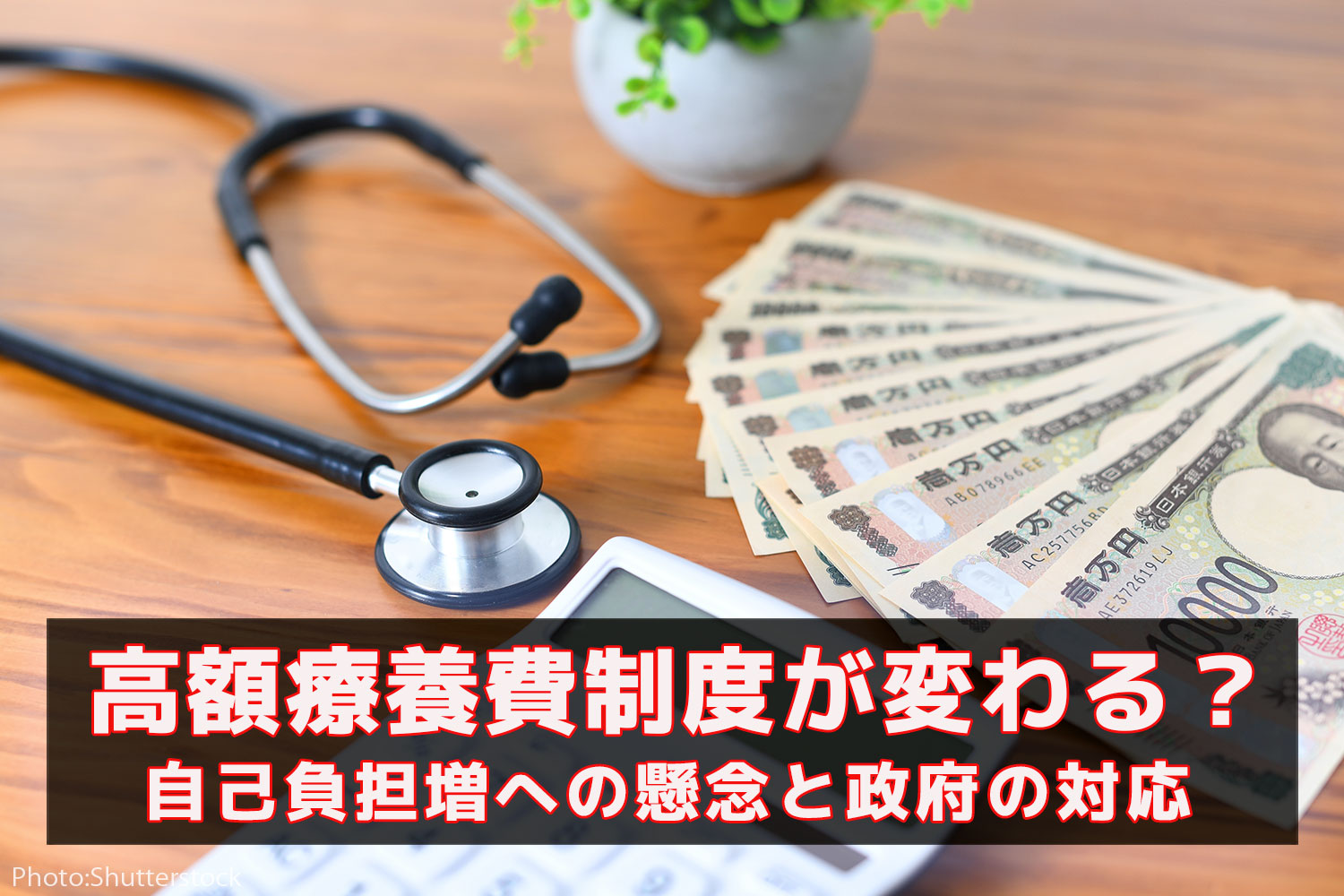高額療養費制度が変わる?自己負担増への懸念と政府の対応
2025.02.21
国会では予算案の審議が行われ、「103万円の壁」「高校授業料無償化」そして「高額療養費の見直し」などについて連日にわたり、与野党での協議が続いています。
高額療養費制度とは
その中の「高額療養費制度」は、同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度で、公的医療保険に加入している方が対象となっています。
公的医療保険には、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、後期高齢者医療制度、共済組合などが含まれます。高額療養費制度を利用すると、自己負担額の限度額を超える分の払い戻しが受けられますが、限度額は、一般的に年齢や所得に応じて定められ、加入する保険によっても異なります。また、固定の金額ではなく、発生した医療費によっても変動します。
高額療養費制度の適用件数は高齢化や高額な新薬の登場により、21年度までの10年間で3割増えています。医療費が高額になる中、高額療養費制度で患者負担が一定額に抑えられ、患者の実質的な負担割合は低下傾向にあるとのことです。
歳出における医療、年金、介護などをあわせた社会保障関係費が増加を続ける中で、今回「高額療養費制度」の見直しを2015年以来、10年ぶりに掲げています。今回の見直しでは支払い能力に応じて負担を求める「応能負担」を強め、医療の保険給付を抑制し、現役世代に偏りがちな保険料負担の軽減も狙うとの考え方です。

患者団体の反発と懸念
しかし、患者団体などから、自己負担が増えれば治療を続けるのが難しくなるなどの声が上がっています。全国がん患者団体連合会(全がん連)が1月17〜19日に実施したアンケートでは、患者やその家族、医療関係者など3000人超の意見が集まり、上限引き上げを懸念する指摘が相次ぎました。また高額療養費の見直し案を巡っては年収だけを基準にするため、現役世代で引き上げ幅が大きくなりやすく、現役世代からも反対する声が出ています。
政府の対応と見直しの修正
こうした世論の状況を受け、福岡資麿厚生労働相は2月14日にがんなどの患者団体との面会で、医療費が高くなった場合に「高額療養費制度」の見直し案を修正し、「長期の治療を受けた患者については負担額を変更しない」と表明しました。これは直近12カ月以内に3回限度額に達した場合、4回目から限度額を下げる「多数回該当」の限度額引き上げを見送るというもので、自己負担が増えれば治療を続けられなくなるといった多くの患者からの声に配慮した形です。
さらに2月17日の衆議院予算委員会で石破茂首相は「高額療養費制度」の限度額を引き上げる見直し案の修正に言及しました。厚生労働省は当初、この限度額について、2025年8月から27年8月にかけて段階的に引き上げる方針を示しており、1カ月あたりの額とともに、直近12カ月以内に3回上限に達した場合、4回目から額を下げて対応する「多数回該当」の額を上げることを想定していました。
首相は「年4回以上該当する方の自己負担額の見直しの凍結を政府として決断した」とし、「長期にわたって治療を継続している方々の不安の声があった」と述べています。
立憲民主党による対抗策
世論を受けた政府の動きがありましたが、立憲民主党は2月19日に「高額療養費制度」の利用者負担を引き上げる政府方針を凍結するため、健康保険法などの改正案を衆議院に提出しました。この改正案では、高額療養費を長期間受給する患者について、家計や治療に与える影響を考慮するとともに、生活実態の調査も求めるとしています。

高額療養費制度の見直しに求められる慎重な対応
今回の予算案審議は、「103万円の壁」で国民民主党が、「高校授業料無償化」で日本維新の会が、政府・与党へ強く働きかけを行っており、立憲民主党は「高額療養費見直し」を強く取り上げることで参議院選挙に向けた存在感をアピールしたいところと思われます。
「高額療養費制度」は増加が続く歳出の社会保障関係費の軽減に繋がる重要な事案ですが、国民の誰もが抱える健康とくらしに直結する内容だけに、改正案の提出者である立憲民主党の中島克仁政調会長代理の発言にある「患者が治療をやめる事態を招かないようにしなければならない」を政府は重く受け止め、慎重に検討をしていただきたいと思います。