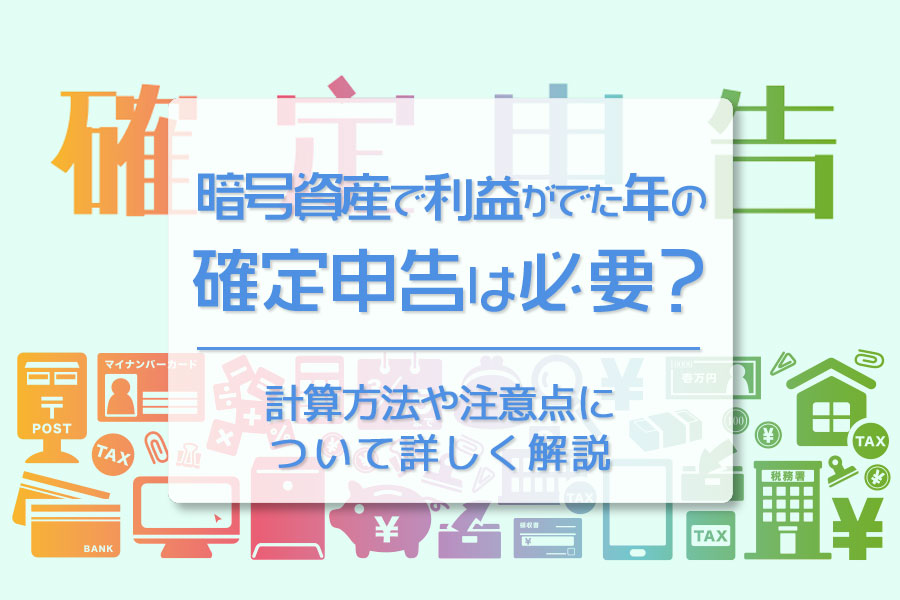仮想通貨(暗号資産)で利益がでた年の確定申告は必要? 計算方法や注意点について詳しく解説
2024.11.01
仮想通貨(暗号資産)取引は単に日本円と交換する以外にも、銘柄同士を交換したりマイニングやレンディングを利用したりと、特殊なケースがあります。確定申告が必要となる具体的な状況を理解しておかなければ、正しい手順で確定申告ができず、ペナルティが課される可能性があるでしょう。
そこで本記事では、仮想通貨(暗号資産)取引に関わる確定申告の概要や、確定申告が必要となる4つのタイミングなどを解説します。あわせて仮想通貨(暗号資産)取引で得た利益の算出方法や、確定申告の注意点などもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
仮想通貨(暗号資産)で利益が出たら確定申告する?
仮想通貨(暗号資産)に関わる確定申告について解説する前に、確定申告の概要から見ていきましょう。
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間で得た収益から経費を差し引いて所得を算出し、所得税を国に申告して納税する一連の流れです。申告の期間は特別な場合を除き、翌年の2月16日から3月15日までと定められており、これを過ぎるとペナルティが課される可能性があるので注意が必要です。
多くの給与所得者は、会社が行う年末調整で所得税額が決定され、代理で納税してくれるため必要はありません。しかし、以下に該当する人は確定申告が必要となります。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| (1)給与所得がある方 | 給与所得が2,000万円を超える 給与所得と退職所得以外の合計金額が20万円を超えるなど |
| (2)公的年金の雑所得のみの方 | 公的年金から所得控除を引くと、残額がある |
| (3)退職所得がある方 | 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある |
| (4)上記以外の方 | 所得税額から配当控除額を差し引き、残額がある |
仮想通貨(暗号資産)取引を行う人の場合、主に(1)(3)(4)に該当する可能性があります。次章からは、仮想通貨(暗号資産)取引における確定申告の詳細を解説します。
仮想通貨(暗号資産)の勘定科目は雑所得
以下の表は、所得税法で定められている所得の分類です。
| 所得名 | 概要 |
|---|---|
| 利子所得 | 預貯金・公債などの収益の分配による所得 |
| 配当所得 | 株式・投資信託の収益の分配による所得 |
| 不動産所得 | 不動産事業や譲渡で得た所得 |
| 事業所得 | 不動産や山林関連以外の事業で得た所得 |
| 給与所得 | 勤務先から受け取る給与や賞与などの所得 |
| 退職所得 | 退職の際に受け取る所得 |
| 山林所得 | 山林の譲渡による所得 |
| 譲渡所得 | 土地・建物・ゴルフ会員権などの資産の譲渡による所得 |
| 一時所得 | 利子所得から譲渡所得に該当しない一時的な所得(賞金や払戻金、保険の満期返戻金など) |
| 雑所得 | 利子所得から一時所得に該当しない所得(公的年金、副業による所得など) |
このうち、仮想通貨(暗号資産)は雑所得に分類されます。
仮想通貨(暗号資産)は総合課税の対象
仮想通貨(暗号資産)取引で得た所得は総合課税の対象なので、給与所得や事業所得、雑所得などと合算され課税されます。
所得税は以下の表のように累進課税制度が導入されており、所得金額に応じて5%から45%の幅で設定されています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上表に基づくと、給与所得が300万円なら税率は10%です。ここに仮想通貨(暗号資産)取引での利益が30万円加わると、課税される所得金額の合計は330万円となり税率は20%に上がります。
株式や投資信託による所得とは扱いが異なる
仮想通貨(暗号資産)取引に関わる所得は、申告分離課税の対象となる株式や投資信託による所得とは扱いが異なります。申告分離課税では、他の所得とは分離されて税額が決まる点が特徴です。
例えば、給与所得が300万円に加えて株式や投資信託による所得が30万円ある場合、前者の300万円に対しては上表より10%、後者の30万円に対しては20.315%が課税されます。

仮想通貨(暗号資産)が課税対象になる4つのタイミング
仮想通貨(暗号資産)取引では、以下のタイミングで発生した利益は課税対象となります。
- 仮想通貨(暗号資産)を売却したとき
- 仮想通貨(暗号資産)で決済をしたとき
- 保有している仮想通貨(暗号資産)で別の仮想通貨(暗号資産)を購入したとき
- マイニングやレンディングで仮想通貨(暗号資産)を取得したとき
いずれのケースでも、取引手数料や諸経費、他の雑所得の損失を差し引いて所得金額が20万円以上あるなら、確定申告が必要です。
各内容を具体例を交えながら見ていきましょう。
1.仮想通貨(暗号資産)を売却したとき
保有している仮想通貨(暗号資産)を売却したときは、利益が発生すると課税対象となります。所得金額は、以下の式で算出されます。
所得金額 = 売却価額 – (取得時1単位あたりの価額 × 売却した数量)
例えば、1BTC=100万円のときに0.3BTC(30万円分)購入するケースを考えてみましょう。1BTC=500万円に価格上昇した際に0.1BTC分の50万円売却すると、50万 – 10万円(100万円×0.1BTC)=40万円が所得金額となります。
2.仮想通貨(暗号資産)で決済をしたとき
仮想通貨(暗号資産)で決済をした際、一度換金して決済したとみなされるため課税対象となります。所得金額は、以下の式で算出されます。
所得金額 = 購入した商品価額 – 仮想通貨(暗号資産)取得時の価額
例えば、1BTC=100万円のときに1BTC購入し、評価額が200万円になったときに20万円のパソコンを0.1BTCで購入したとします。この場合の所得金額は、20万円 – 100万円/BTC×0.1BTCより10万円です。
3.保有している仮想通貨(暗号資産)で別の仮想通貨(暗号資産)を購入したとき
仮想通貨(暗号資産)の銘柄同士の交換や購入は、実際は法定通貨に換金していませんが課税対象となる点には注意してください。仮想通貨(暗号資産)Aで仮想通貨(暗号資産)Bを購入した際、所得金額は以下の式で算出されます。
所得金額 = 仮想通貨(暗号資産)Bの購入価額 – 仮想通貨(暗号資産)Aの譲渡原価
例えば、1BTC=100万円のとき1BTC購入し、それをすべて使って1ETH=40万円のときに3ETH分購入したとします。イーサリアム(ETH)の購入価額は120万円なので、このときの所得金額は120万円 – 100万円より20万円です。
4.マイニングやレンディングで仮想通貨(暗号資産)を取得したとき
マイニングやレンディングで仮想通貨(暗号資産)を取得した際は、利益とみなされるので確定申告が必要になる可能性があります。
マイニングとは、仮想通貨(暗号資産)のトランザクションを検証・承認し、データをブロックチェーンに付加する作業です。銘柄によって細かいアルゴリズムは異なりますが、マイニングを行うと報酬を得ることができます。確定申告する際は、マイニングにかかった電気代やパソコン代などの費用を、経費にするのを忘れないようにしましょう。
一方、レンディングとは、保有する仮想通貨(暗号資産)を第三者に貸し出し利息を得る運用方法を指します。仮想通貨(暗号資産)を保有し、ブロックチェーンネットワークに貢献することで報酬が貰えるステーキングにより得た仮想通貨(暗号資産)の売却も、課税所得の対象です。
確定申告が必要ないケース
ここまでは、仮想通貨(暗号資産)取引で確定申告が必要になるケースを解説しましたが、以下のように不要な場合もあります。
- ハードフォークにより仮想通貨(暗号資産)を取得した場合
- 海外在住の方が保有する仮想通貨(暗号資産)を日本の取引所で売却した場合
- 仮想通貨(暗号資産)を保有し続けている場合
各ケースの概要を解説します。
ハードフォークとは、ブロックチェーンの仕様変更に伴い、既存の仮想通貨(暗号資産)から新たな仮想通貨(暗号資産)が誕生することです。過去には、ビットコイン(BTC)コミュニティ内の対立から、ビットコインキャッシュ(BCH)が誕生しました。
ハードフォークで新たな仮想通貨(暗号資産)を得た場合、その時点では課税対象となる所得とはみなされません。その後売却した際は、取得価額を0円として所得金額が計算されます。
海外在住の方が日本の仮想通貨(暗号資産)取引所で取引をした場合も、基本的に確定申告は必要ありません。ただし、居住している国の法制度に則った手続きが必要になる可能性があるため、確認しましょう。
また評価額が上昇しても、仮想通貨(暗号資産)を保有するだけなら課税対象となる所得は発生しません。

仮想通貨(暗号資産)で得た所得額の計算方法
仮想通貨(暗号資産)取引で得た利益の算出方法は、大きく分けて「移動平均法」と「総平均法」の2つです。
1回だけ取引をした場合と、複数回取引をした場合で両者の計算方法は異なるのでそれぞれ見ていきましょう。
1回だけ取引をした場合
1BTC = 200万円のときに3BTC購入し、その後300万円に値上がりした際に1BTC売却するという、1回だけ取引をするケースの所得金額(利益)の算出方法を解説します。
上記のシンプルなケースでは、移動平均法と総平均法で計算方法は変わらず、所得金額は譲渡金額の300万円から譲渡原価の200万円を引いて、100万円です。
複数回取引をした場合
以下のように複数回取引をする場合を考えてみます。
- 4月10日、1BTC = 100万円で1BTC購入(保有量1BTC)
- 5月10日、1BTC = 150万円で1BTC購入(保有量2BTC)
- 8月15日、1BTC = 200万円で1BTC売却(保有量1BTC)
- 10月20日、1BTC = 200万円で1BTC購入(保有量2BTC)
- 12月20日、1BTC=300万円で1BTC売却(保有量1BTC)
1年間の売却額(数量)の総額は500万円(3BTC)、購入額(数量)の総額は450万円(6BTC)ですが、移動平均法と総平均法で計算方法が異なるので詳しく見ていきましょう。
購入のたびに計算する「移動平均法」
移動平均法は、購入するたびに「保有総額 ÷ 数量」より平均単価を算出します。
以下は、8月15日に売却するまでの取引における計算経過です。
- 1. 4月10日と5月10日の平均レート:(100万円 + 150万円) ÷ 2BTC = 125万円/BTC
- 2. 8月15日に売却した1BTCの取得時価額:1BTC × 125万円 = 125万円
- 3. 8月15日の取引で得た所得金額(売却価額と取得時価額の差):200万円 – 125万円 = 75万円
次に、12月20日に売却する取引の所得金額を算出します。
- 1. 10月20日時点での平均レート:(125万円 + 200万円) ÷ 2BTC = 162.5万円/BTC
- 2. 12月20日に売却した1BTCの取得時価額:1BTC × 162.5万円 = 162.5万円
- 3. 12月20日の取引で得た所得金額:300万円 – 162.5万円 = 137.5万円
8月15日と12月20日の取引の所得金額を求めたら、それぞれを足し合わせます。今回のケースで移動平均法を使って所得金額を求めると、75万円 + 137.5万円より212.5万円です。
続いては総平均法の計算方法を見ていきましょう。
1年を通じて計算する「総平均法」
総平均法では、年初時点で保有する仮想通貨(暗号資産)の評価額と年間で取得した総額を、年末時点の保有量で除して平均単価を求めます。
- 購入時の平均レート:(100万円 + 150万円 + 200万円) ÷ 3BTC = 150万円/BTC
- 取得時価額:150万円/BTC × 2BTC = 300万円
- 売却価額:(200万円 + 300万円) = 500万円
- 所得金額:500万円 – 300万円 = 200万円
同じ取引ですが、移動平均法と総平均法では所得金額に12.5万円の差が生まれました。ここで、移動平均法と総平均法のそれぞれの違いを把握しておきましょう。
移動平均法の特徴は、以下のとおりです。
- 取得する度に計算するので、煩雑になる
- 実際の取引の利益と所得金額が近くなる
- 所得金額を予想しやすいので、納税の準備ができる<
一方、総平均法の特徴は以下のとおりです。
- 年内の取引をまとめて所得金額を出すので、計算が簡単
- 実際の取引の利益と所得金額がかけ離れる可能性がある
- 所得金額は年度が終わらないと出せないので、納税の準備がしづらい
国税庁は、同一の仮想通貨(暗号資産)を複数回にわたって取引した場合は、移動平均法を利用するのを推奨しています。
ちなみに今回の取引では、移動平均法と総平均法で所得金額が異なりましたが、通年で計算すると最終的に所得金額は一致します。

仮想通貨(暗号資産)で確定申告をする際の注意点
仮想通貨(暗号資産)取引に関わる確定申告では、以下の点に注意してください。
- 評価方法は仮想通貨(暗号資産)の種類ごとに決める
- 仮想通貨(暗号資産)は損益通算できない
- 必要経費もきちんと計上する
- 確定申告しないとペナルティを科せられる
取引や確定申告の手続きをする前に、必ず各内容を押さえておく必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
評価方法は仮想通貨(暗号資産)の種類ごとに決める
仮想通貨(暗号資産)取引の評価方法である総平均法と移動平均法は、「初めて仮想通貨(暗号資産)を取得した場合」と「異なる種類の仮想通貨(暗号資産)を取得した場合」に届け出なければなりません。つまり、評価方法は銘柄ごとに設定する必要があります。
原則として確定申告期限までに納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出します。総平均法と移動平均法の違いを把握し、どちらにするかを事前に決めましょう。
なお、届出がない場合は、総平均法が選択されます。
仮想通貨(暗号資産)は損益通算できない
仮想通貨(暗号資産)は雑所得のため、節税手段の一つである「損益通算」ができません。損益通算とは同一年度の利益と損失を相殺する方法ですが、雑所得は他の区分所得とは通算できないからです。そのため、仮に仮想通貨(暗号資産)取引で損失が出た場合、それを給与所得や事業所得などの他の所得から差し引くことはできないのです。
不動産投資を行っている方が土地購入のために資金を借り入れ、損失が100万円だった場合、給与所得や事業所得から損失額の100万円を差し引いて所得税が計算されます。
一方の仮想通貨(暗号資産)の場合、給与所得が500万円、仮想通貨(暗号資産)取引にかかる損失が100万円でも、得た所得を400万円と計算できません。そのため、所得税が多くなる点には注意しましょう。
また、損失の繰越控除もできません。上場株式の取引ならば、損失を最大3年間繰り越して翌年度以降の利益から控除できますが、仮想通貨(暗号資産)取引の損失は繰越控除ができないため、昨年度の損失が100万円でも、今年度の所得から引くことはできない点には注意してください。
必要経費もきちんと計上する
節税するためには、必要経費をきちんと計上する必要があります。一般的に仮想通貨(暗号資産)取引で認められる必要経費には、以下のものが挙げられます。
- 仮想通貨(暗号資産)の譲渡原価
- 取引所利用に関わる手数料
- 取引に必要な分の通信費や電気代
- 仮想通貨(暗号資産)のセミナーや書籍に関わる費用
上記以外にも、所得を生み出すために必要と認められる費用に限り、必要経費として計上できます。
しかし必要以上に経費計上して過少に税金を納めると、納税すべき額の10%〜15%の過少申告加算税、または35%〜40%の重加算税が課せられる場合があります。仮想通貨(暗号資産)関連だからといって、全てを経費計上しないようにしてください。
確定申告しないとペナルティを科せられる
所得税法により、確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間に行い、所得税を納付しなければなりません。それ以降の申告は期限後申告として扱われ、納めるべき税金に加えてペナルティとして無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、50万円部分までは15%、50万円を超える部分には20%課されます。納税額が100万円だった場合、無申告加算税は50万円×15% + 50万円×20% = 17.5万円です。ただし、期限後申告であっても以下のケースでは無申告加算税は課されません。
- 期限後申告が期限後1カ月以内に自主的に行われる
- 期限内申告をする意思がある(期限後すぐに納税している・過去5年までの間にペナルティを課されていない)
また期限後申告での納期限は、申告した日ですが、それ以降に納税すると延滞税が課される可能性もあります。延滞税の割合は、納税額によっても異なりますが、「納付金額 × 延滞税の割合 × 過ぎた日数」で計算されます。

確定申告にも対応できるBitLendingで仮想通貨(暗号資産)を預けて増やそう
本記事では仮想通貨(暗号資産)取引に関わる確定申告の概要や、所得額の算出方法、確定申告時の注意点を解説しました。仮想通貨(暗号資産)は特殊な取引が多く複雑になりがちですが、確定申告が必要な場合に行わないとペナルティが課される可能性があるので注意しましょう。
なお、頻繁に取引を繰り返す現物取引やアービトラージでは、所得の算出方法が複雑になります。なるべく取引回数を減らしつつ、しっかり利益も狙いたい方はプロの手によるレンディングがおすすめです。
プロの手によるレンディングサービスは自分で運用する必要がなく、難しい知識も不要ながら銀行預金よりも高い利率で運用できる点がメリットです。
レンディングサービスを提供するBitLendingでは、以下の銘柄を表記の利率で運用できます。

ビットコイン
BTC
8%
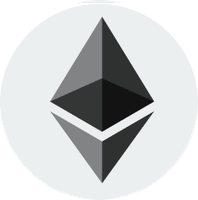
イーサリアム
ETH
8%

リップル
XRP
7%
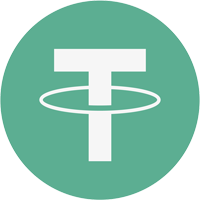
USテザー
USDT
10%

USDコイン
USDC
10%
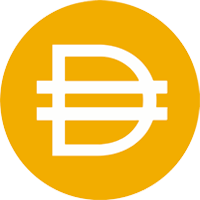
ダイ
DAI
10%
時価総額ランキングで上位のビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)・リップル(XRP)に加え、価格が安定して推移するステーブルコインのUSテザー(USDT)・USDコイン(USDC)・ダイ(DAI)を取り扱っています。
加えて仮想通貨(暗号資産)の確定申告をシンプルに行えるソフトとの連携が可能なので、確定申告もスムーズに行えます。
確定申告も簡素化した運用をしたいと考えている方は、ぜひBitLendingのご利用をご検討ください。